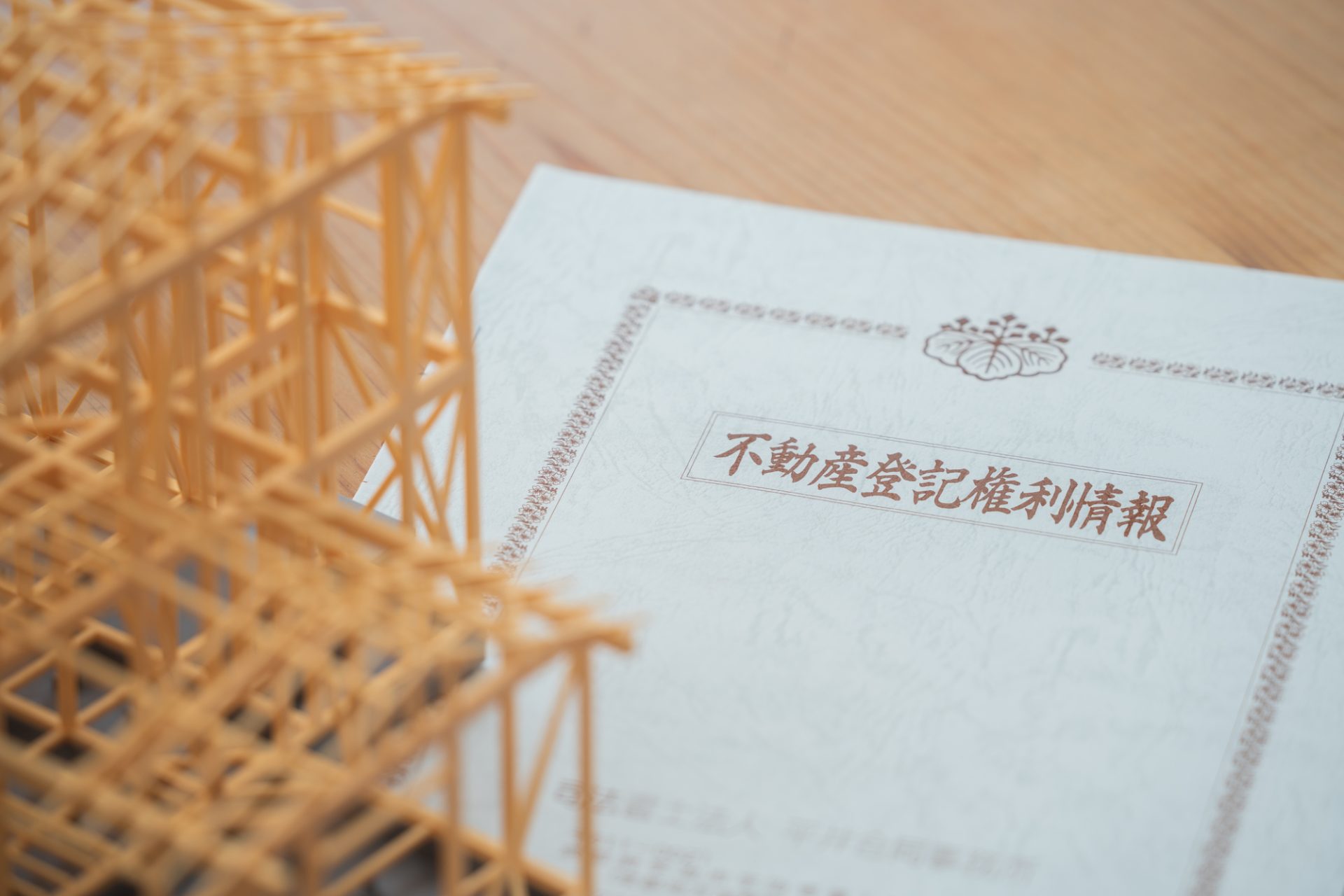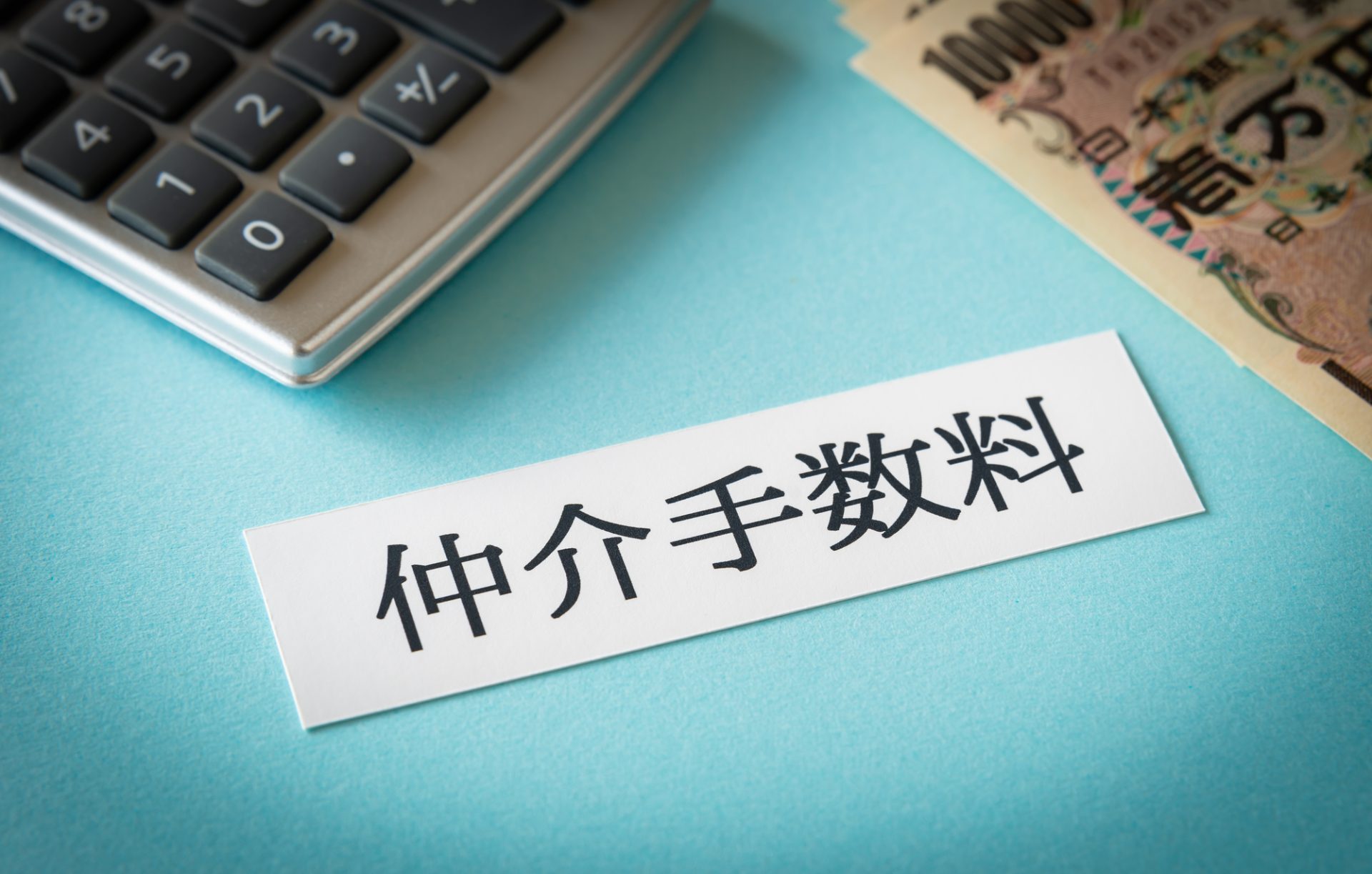マイホームの購入を考えたとき、問題になるのが予算と支払い方法です。何千万円もの支払いを一括で行うのは難しいため、多くの人がローンを利用することになります。しかし、ローンには利息が発生するため「ある程度資金を貯めてから購入するべきか?」と悩むこともあるでしょう。
この記事では、家を購入するタイミングやローンを利用するメリット、借入額の考え方を解説します。ローンの注意点もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
目次
家を購入するならいつ?
家を購入するタイミングは頭金の有無で変わります。まずは「頭金なしで早めに購入するケース」「資金を貯めてから購入するケース」を比較してみましょう。
ローンで早めに購入するケース
頭金がなくてもローンを借り入れることで、家を早めに購入できます。かつては頭金がないと住宅ローンを借りにくいといわれていましたが、現在では頭金がなくても借り入れが可能なケースが少なくありません。
頭金を支払わない場合、借入額が増えて利息の負担が大きくなるものの、住宅ローン控除制度による所得税の控除額は上がります。住む家が手に入るため家賃の支払いがなくなる点も、早めに購入するメリットです。
資金を貯めてから購入するケース
頭金に使う資金を貯めてから、住宅ローンを借り入れて家を購入する方法もあります。はじめに頭金を支払うことで借入金を減らし、毎月の返済額と利息の負担を軽減できます。
ただし、資金を貯めている期間中は、それまで住んでいる住居の家賃の支払いが必要です。また、借入額が減ることで控除の金額が少なくなる可能性も考えられます。
ローンで家を買うメリット
ローンを利用することに抵抗感がある人は少なくありません。一方で、ローンの活用によって金銭的な負担を軽くすることもできます。ここでは、ローンで家を買うメリットを解説します。
家を早く買うことのメリット
ローンを借りて家を早く買えば、家賃の支払いがなくなり、住宅に関する支払いを総合的に抑えることができます。ローンを早いタイミングで借りると完済も早くなり、老後資金を貯める余裕が生まれやすいでしょう。マイホームを購入後、何らかの事情で手放すことになっても、資産価値があれば売却益が手元に残ります。
繰り上げ返済の活用がおすすめ
繰り上げ返済とは、毎月の支払いとは別にまとまった金額を前倒しで返済する方法です。頭金を貯めてから家を購入するよりも、繰り上げ返済を活用した方がトータルコストは安くなります。繰上げ返済によって完済までの期間を短縮し、総返済額も減額できます。繰り上げ返済の金額や時期は柔軟に設定できるので、ライフイベントに合わせて上手に活用していきましょう。
「繰り上げ返済」に関しては下記の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひ参考にしてみてください。
住宅ローンの繰り上げ返済とは?メリットやデメリット、タイミングなど詳しく解説!
家のローンは年齢制限がある
家のローンには年齢制限が設けられていますが、具体的な条件は金融機関ごとに異なります。ここでは、住宅ローンに関わる年齢制限について解説します。
一般的な住宅ローンの年齢制限
多くの金融機関では、住宅ローンの申込可能な年齢と完済時の年齢に制限を設けています。申込可能な年齢とは住宅ローンを借り入れられる年齢のことで、20歳以上70歳以下が一般的です。
完済時の年齢とは住宅ローンを返し終える年齢を指し、基本的には80歳未満となっています。ただし、年齢制限は金融機関やプランによっても異なるため、住宅ローンを借り入れる際に詳細を確認しておきましょう。
完済時の年齢がポイント
住宅ローン審査では完済時の年齢が重視されます。金融機関が住宅ローン審査で考慮する項目は、年収や勤続年数、健康状態など複数あります。
国土交通省が発表した「令和2年度 民間住宅ローンの実態に関する調査 結果報告書」では、審査項目として重視する金融機関が多かったのが完済時年齢で、健康状態、担保評価と続いています。
※参考:令和2年度 民間住宅ローンの実態に関する調査結果報告書|国土交通省
家のローンは何歳までに借りるべき?
住宅ローンに年齢制限が設けられていることを踏まえて、何歳までに借り入れる人が多いのかを見ていきましょう。
40歳前後でローンを組む人が多い
住宅ローンの審査では、借入時と完済時の年齢が重視されます。住宅金融支援機構が発表した「2022年度フラット35利用者調査」では、2022年度における借入時の平均年齢は42.8歳という結果でした。住宅ローンの利用者は30歳代、40歳代がボリュームゾーンですが、平均年齢は上昇傾向にあります。
※参考:2022年度フラット35利用者調査|住宅金融支援機構
35年ローンを組むための上限年齢
多くの金融機関で、住宅ローンは最長35年までとなっています。35年ローンの場合、年齢だけを見れば44歳まで申し込むことが可能です。しかし、ローン審査では完済時年齢が重視されるため、高齢になるほど審査に通りづらくなる傾向です。借入額や年収から、自分にとっての上限年齢を考える必要があります。
65歳までの完済が理想的
住宅ローンは65歳までの完済が理想的です。65歳までに定年となる企業が多く、定年後は収入の減少が予想されます。住宅ローンの返済計画を立てる際は、安定した収入が見込める65歳までを目標とするとよいでしょう。
家のローンで気をつけたいポイント
家のローンでは、年齢制限以外にも気をつけたいポイントがあります。それぞれの注意点を知り、無理のない返済計画を立てましょう。
住宅ローンの金利は主に3種類
住宅ローンの金利には、次の3種類があります。
- 全期間固定金利型
- 変動金利型
- 固定金利期間選択型
毎月決まった金額を返済したい場合は、全期間固定金利型がおすすめです。変動金利型は、金利が低く設定されていますが、市場金利が上昇すると返済額が増加するリスクがあります。金利を抑えつつ、上昇によるリスクを低減したいなら、固定金利期間選択型が向いています。
金利の種類ごとにメリットとデメリットがあるため、自分の状況や条件に合ったタイプを選択することが重要です。
無理なく返済できる借入額にする
借入額が大きくなるほど、家計への負担も増加します。結婚や出産などのライフイベントでは大きな出費が発生するため、余裕を持った返済計画を立てることが大切です。現在の状況だけでなく、長期的な視点で無理なく返済できる借入額を考えていきましょう。
住宅ローンには諸費用がかかる
住宅ローンを借り入れると、返済額の他に諸費用が発生します。諸費用としては、次の項目が挙げられます。
- 印紙税
- 融資関係手数料
- ローン保証料
- 地震・火災保険料
- 団体信用生命保険料 など
諸費用の負担を見積もったうえで、住宅ローンを組むことが重要です。
追加融資は基本的に難しい
住宅ローンを申し込んだ後に「借入額を増やせばよかった」と後悔する人は少なくありません。たとえば、住宅の建築に想定より費用がかかった場合は、追加で借り入れたいと考えることもあるでしょう。しかし、基本的に追加融資は難しいため、建築費用を正確に算出することを心がけましょう。
無理なく返済できるローンは?
ここでは、無理なく返済できる借入額を「年収」「家賃」という2つの観点から解説します。
年収から考える借入額
一般的に、年収の25%以内が無理なく支払える年間返済額とされています。たとえば、年収600万円で金利1.7%、35年返済、元利均等、ボーナス時加算なしの場合、3,950万円が借入額の目安となります。
ただし、同じ年収でもライフスタイルなどで月々に返済可能な金額は異なるため、毎月の返済額やボーナス時の加算なども考慮して借入可能額を算出していきましょう。
家賃から考える借入額
年収ではなく、現在の家賃から無理なく返済可能な借入額を考える方法もあります。現在の家賃と住宅ローンの毎月返済額が同額なら、同じように支払いを続けていけるでしょう。
たとえば、毎月の家賃が10万円で家賃と同額の返済額となるケースを想定してみます。この場合、金利1.7%で35年返済、元利均等、ボーナス時加算なしで契約すると、3,160万円が無理なく返済できる借入額となります。
家を買うのに必要な頭金
頭金がなくても家を買うことはできますが、実際はどれくらいの資金を用意する人が多いのでしょうか。最後に、頭金の目安と考慮すべきポイントを解説します。
頭金とは?
頭金とは、家を購入するにあたって、最初に支払うまとまった代金のことです。頭金を支払うことで借入金を減らし、利息の負担を軽減できます。頭金は購入費用の1~2割を支払うケースが多いですが、1割未満で購入を決断する人も増加しています。
※参考:2022年度フラット35利用者調査|住宅金融支援機構
諸費用や生活予備費を考慮しよう
頭金が多ければ住宅ローンの総返済額を減らせるものの、ある程度の資金を手元に残しておくことも重要です。特に、住宅ローンの借り入れでは諸費用が発生するため、支払いに備えておかなければなりません。
病気やケガ、休職などの問題が発生した際、円滑に対処できるよう生活予備費を確保しておく必要もあります。貯蓄をすべて使うのではなく、諸費用や生活予備費などを差し引いた金額を頭金として用意しましょう。
まとめ
住宅ローンの利用には、さまざまな制限や条件が設けられています。特に、年齢に関しては申込時だけでなく完済時にも制限があるため、選択肢を広げるためには若いうちに借り入れを始めることが大切です。
ハウスドゥは、不動産に関する幅広い情報を発信しております。全国展開しているネットワークを活用し、不動産に関するさまざまなサービスをワンストップで提供しています。住み替えを検討されている人や住宅ローンについて詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
AIで不動産査定!
AIがお持ちの不動産の市場相場を診断