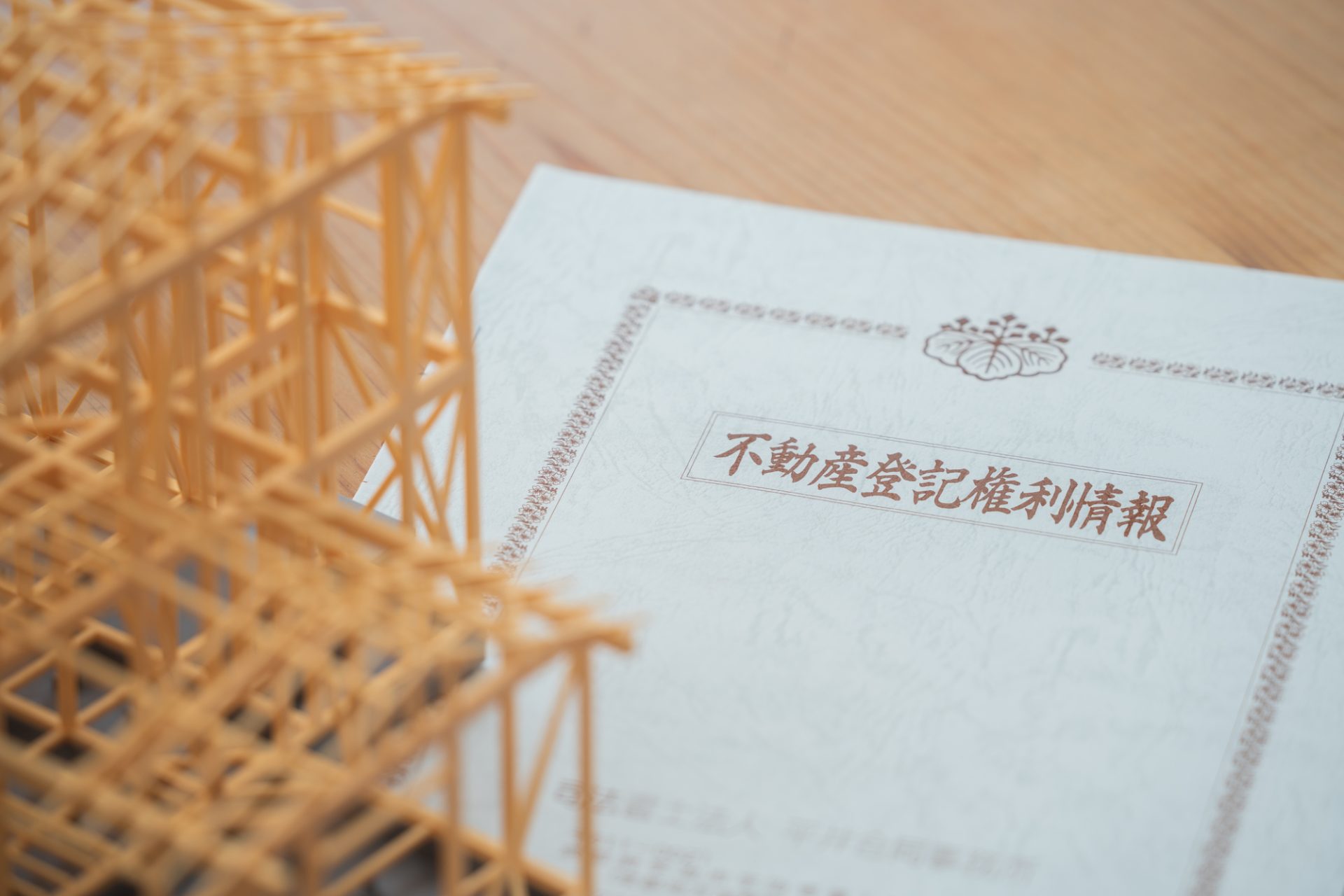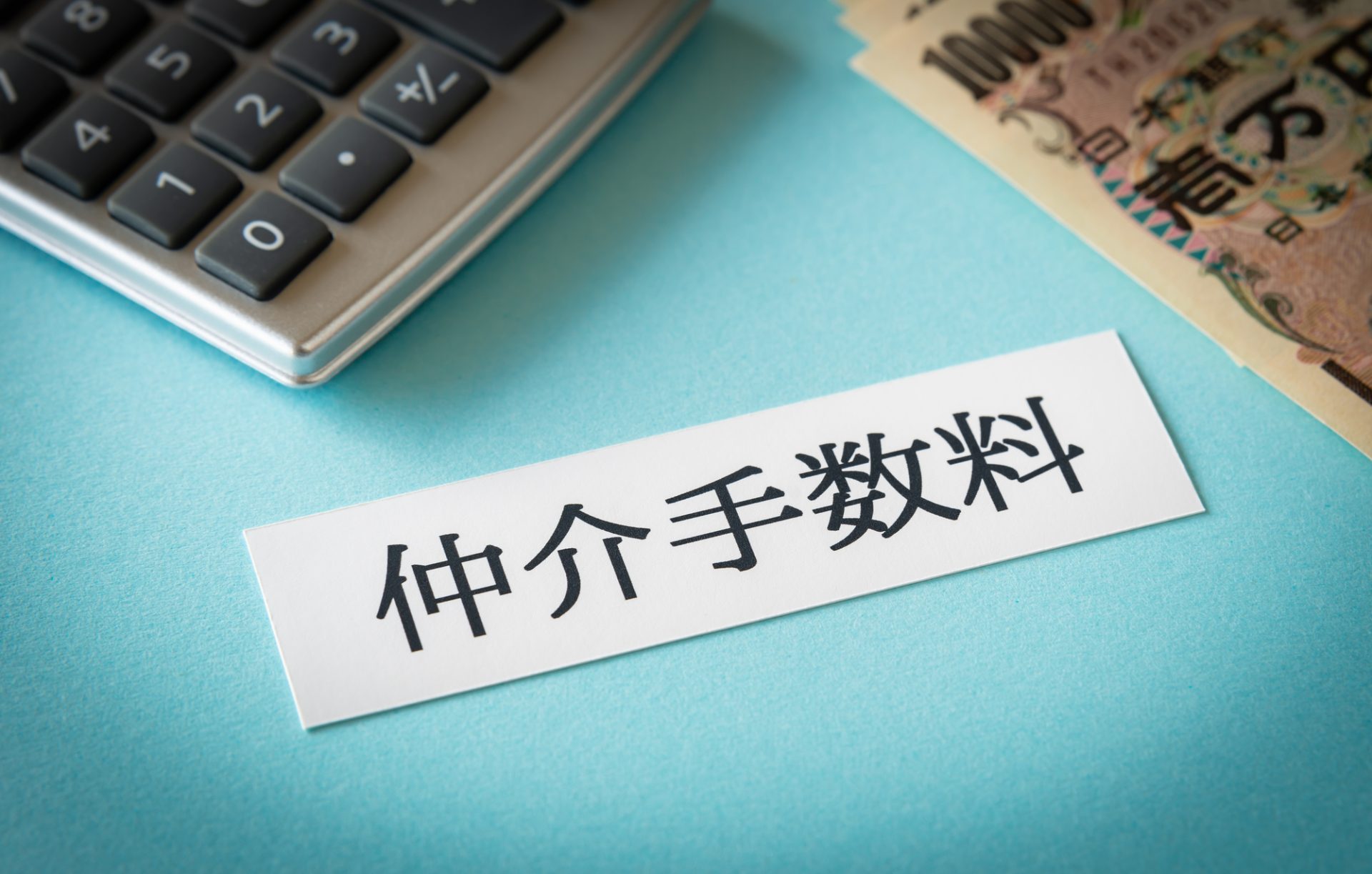「マンションの固定資産税って、結局いくら払うことになるんだろう?計算も複雑そうだし、知らないうちに損をするのは絶対に避けたいな…」
そう思う方もいるかもしれません。
実は、固定資産税の金額は「評価額」と「軽減措置」の2つのポイントを理解すれば、ご自身でもおおよその計算ができ、払いすぎを防ぐことも可能です。
この記事では、マンションの固定資産税の相場や具体的な計算方法から、税金を安くする軽減措置、支払い方法まで、あなたが損をしないための知識を網羅的に解説します。
この記事のポイント
- マンション固定資産税の相場は年間10万~30万円が目安
- 税額は「固定資産税評価額」と「軽減措置」で決まる
- 新築マンションは最初の5年間、税金が半分になる特例がある
- 納税通知書は毎年4月~6月頃に届き、年4回に分けて支払う
目次
マンションの固定資産税はいくら?価格・築年数別の相場をシミュレーション
「結局、うちのマンションはいくらになるの?」という疑問は、誰もが思うことでしょう。
具体的なシミュレーションを見れば、ご自身の状況に近いおおよその金額が把握できます。
- 全体の平均相場は年間10万~30万円が目安
- 価格帯別シミュレーション(2,000万円・4,000万円・6,000万円の例)
- 築年数別シミュレーション(築10年・20年・30年の例)
さっそく、全体の相場から見ていきましょう。
全体の平均相場は年間10万~30万円が目安
まず結論からお伝えすると、マンションの固定資産税の年間相場は、多くの場合10万円から30万円の範囲に収まります。
初めてマンションを購入する方は、この金額を一つの目安として資金計画に含めておくと良いでしょう。
ただし、これはあくまで一般的な目安の金額。
実際の税額は、マンションがどこにあるのか(立地)、どれくらいの広さなのか(専有面積)、いつ建てられたのか(築年数)といった様々な条件によって大きく変動します。
特に、東京都心部のような地価の高いエリアにある物件や、専有面積が広いファミリータイプの物件、最新設備を備えた築浅の物件ほど税額は高くなる傾向にあります。
これから解説する具体的なシミュレーションを参考に、ご自身の状況に近いケースを確認してみてください。
価格帯別シミュレーション(2,000万円・4,000万円・6,000万円の例)
ここでは、新築マンションの購入価格別に固定資産税がいくらになるか、簡単なシミュレーションを見ていきます。
一般的に、固定資産税の計算の元となる「固定資産税評価額」は、実際の購入価格の70%程度が目安とされています。
また、新築マンションには税金が安くなる軽減措置が適用されるため、その点も考慮して計算することが重要です。
| 購入価格(目安) | 固定資産税評価額(目安) | 年間の固定資産税・都市計画税(軽減措置適用後の目安) |
| 2,000万円 | 1,400万円 | 約7万円~10万円 |
| 4,000万円 | 2,800万円 | 約12万円~16万円 |
| 6,000万円 | 4,200万円 | 約18万円~23万円 |
※上記は一般的な新築マンションの軽減措置(建物の税額1/2、住宅用地の特例)と、都市計画税(税率0.3%)を考慮した概算値です。
この表の金額は、土地と建物の評価額の割合や、お住まいの自治体の税率によっても変わるため、あくまで参考値として捉えてください。
検討している物件のより正確な税額を知りたい場合は、不動産会社の担当者に確認するのが最も確実な方法です。
築年数別シミュレーション(築10年・20年・30年の例)
次に、中古マンションの場合、築年数によって固定資産税がどのように変わるのかを見ていきましょう。
建物は年数が経つにつれて価値が下がっていく(経年劣化)ため、それに伴い建物の固定資産税評価額も少しずつ減少していきます。
そのため、基本的には築年数が古いほど、建物の固定資産税は安くなる仕組みです。
| 築年数 | 新築時からの建物の評価額の下がり方(イメージ) | 固定資産税の傾向 |
| 築10年 | 約20%~30%ダウン | 新築時の軽減措置が終了し一度上がった税額が、経年劣化により少し落ち着いてくる時期です。 |
| 築20年 | 約40%~50%ダウン | 建物評価額が新築時の半分近くまで下がり、税額も比較的安くなる傾向にあります。 |
| 築30年 | 約60%~70%ダウン | 土地の価格が大きく上昇していなければ、税額はかなり抑えられることが期待できます。 |
ただし注意点として、土地の評価額は景気や周辺地域の再開発などによって上昇する可能性があります。
その場合、建物部分の税金が安くなっても、土地部分の税金が上がり、結果として全体の税額があまり変わらない、あるいは逆に上昇するというケースも考えられることを覚えておきましょう。
マンションの固定資産税はどうやって決まる?基本の計算方法
「なぜこの税額になるのか、根拠がわからない」という方も多いでしょう。
計算の仕組みは意外とシンプルです。3つの基本要素で簡単に理解できます。
- 計算の基礎となる「固定資産税評価額」とは
- 固定資産税評価額に税率1.4%を掛けて算出する
- 固定資産税とあわせて請求される「都市計画税」
まずは、計算で最も重要な「固定資産税評価額」から解説します。
計算の基礎となる「固定資産税評価額」とは
マンションの固定資産税を計算する上で、最も重要なのが「固定資産税評価額」です。
これは、皆さんがマンションを購入した際の「購入価格」や、現在の「市場価格(時価)」とは異なる点に注意が必要です。
固定資産税評価額とは、総務省が定めた基準に基づいて、各市区町村が個別に算出・決定する「税金を計算するための公的な価格」のことです。
マンションの場合、自分が所有する「土地(敷地権)」と「建物(専有部分)」のそれぞれに、この評価額が設定されます。
この評価額は、毎年送られてくる納税通知書の「課税明細書」に記載されている「価格」という欄で確認できます。
この金額は原則として3年に1度見直され、これを「評価替え」と呼びます。
景気の変動や街の発展、建物の経年劣化などにより評価額が変わると、固定資産税の額も変動するのです。
固定資産税評価額に税率1.4%を掛けて算出する
固定資産税評価額がわかったら、いよいよ税額の計算です。固定資産税は、以下の計算式で算出されます。
固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4%(標準税率)
ここで「課税標準額」という新しい言葉が出てきました。これは、税率を掛ける直接の対象となる金額のことです。
後ほど詳しく解説する「軽減措置」が適用されると、この課税標準額が固定資産税評価額よりも低い金額になります。
軽減措置がない場合は、「課税標準額=固定資産税評価額」と考えて差し支えありません。
税率の「1.4%」は、地方税法で定められた「標準税率」です。
ほとんどの市区町村ではこの税率が採用されていますが、財政状況などによっては自治体が独自の税率(例えば1.5%など)を定めている場合もあります。
固定資産税とあわせて請求される「都市計画税」
マンションの所有者には、固定資産税とセットで「都市計画税」が課されることが多くあります。
これは、道路や公園、下水道といった都市インフラを整備するための目的税です。
ただし、この税金はすべてのマンションにかかるわけではありません。
原則として、都市計画法で定められた「市街化区域」内に物件がある場合にのみ課税されます。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を指し、日本の多くの都市部がこれに該当します。
都市計画税の計算式は以下の通りです。
都市計画税額 = 課税標準額 × 税率(上限0.3%)
税率は市区町村によって異なり、上限である0.3%に設定している自治体が多く見られます。
納税通知書では固定資産税と合算して請求されることが一般的なので、内訳を確認してみると良いでしょう。
| 税の種類 | 主な目的 | 課税対象となるエリア | 税率 |
| 固定資産税 | 市区町村の行政サービス全般(福祉・教育など) | 全国の固定資産 | 標準1.4% |
| 都市計画税 | 都市計画事業(道路・公園・下水道整備など) | 原則として「市街化区域」内の固定資産 | 上限0.3% |
なぜ固定資産税は上がる?理由と安くするための軽減措置
「税金は法律で決まっているものだから、安くなんてできない」と思っていませんか。
実は、使える制度を知っているか知らないかだけで、税金の負担は大きく変わってきます。
- 新築から6年目に固定資産税が上がるのは軽減措置が終わるから
- 新築マンションなら建物の税金が5年間半分になる
- 土地の税金を安くする「住宅用地の特例」とは
- 軽減措置を受けるのに申請は必要?
まずは多くの方が驚く「税金が上がる理由」から見ていきましょう。
新築から6年目に固定資産税が上がるのは軽減措置が終わるから
新築マンションを購入した方から、「買ってから6年目に、固定資産税が急に高くなった!」という驚きの声がよく聞かれます。
これは故障や間違いではなく、多くの場合、建物の税金を安くする軽減措置の適用期間が終わったことが原因です。
後ほど詳しく解説しますが、新築マンションの建物部分には、新築後5年間にわたって固定資産税が半分になるという大変有利な特例があります。
つまり、最初の5年間は割引された税額を支払っており、6年目から本来の税額に戻るだけなのです。
この仕組みを知らずにいると、6年目の納税通知書を見て「こんなに高いなんて聞いてない!」と慌ててしまうことになりかねません。
新築マンションを購入する際は、数年後には税額が上がることをあらかじめ資金計画に織り込んでおくことが非常に重要です。
なお、認定長期優良住宅の場合は軽減期間が7年間なので、税額が本来の額に戻るのは8年目からとなります。
新築マンションなら建物の税金が5年間半分になる
それでは、6年目に税額が上がる原因となる「新築マンションの軽減措置」について具体的に見ていきましょう。
これは、新築住宅の購入を促進するために設けられた制度です。
一定の要件を満たす新築マンションの場合、新築後5年間にわたり、建物(居住部分120㎡まで)にかかる固定資産税が2分の1に減額されます。
| 適用要件 | ・2026年(令和8年)3月31日までに新築された住宅であること ・居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること |
| 軽減内容 | ・一般のマンション:新築後5年間、建物の固定資産税を1/2に減額 ・認定長期優良住宅:新築後7年間、建物の固定資産税を1/2に減額 |
この制度があるおかげで、新築後の数年間は住宅ローンの返済と並行しながらも、税金の負担を軽くすることができます。
マンションの購入を検討する際は、このメリットを最大限に活用したいところです。
土地の税金を安くする「住宅用地の特例」とは
建物だけでなく、マンションが建っている「土地」にも非常に重要な軽減措置があります。
それが「住宅用地の特例」です。
この特例は、新築・中古を問わず、居住用の家屋が建っている土地に自動的に適用される、非常に重要な仕組みです。
具体的には、土地の課税標準額が以下のように大幅に減額されます。
- 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡までの部分) → 課税標準額が評価額の6分の1
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分) → 課税標準額が評価額の3分の1
マンションの場合、敷地全体の面積を総戸数で割った一人当たりの土地の持分が200㎡を超えることは稀です。
そのため、ほとんどのケースで最も割引率の高い「6分の1」が適用されることになります。
この特例があるからこそ、土地の固定資産税は思ったよりも高額にならずに済んでいるのです。
軽減措置を受けるのに申請は必要?
ここまで解説してきた軽減措置ですが、「自分で何か申請しないと適用されないの?」と不安に思う方もいるかもしれません。
結論から言うと、原則としてこれらの軽減措置を受けるための特別な申請は不要です。
新築マンションが完成すると、市区町村の職員が建物の評価額を決めるための「家屋調査」に訪れます。
その調査結果や登記情報をもとに、自治体側が軽減措置の要件を満たしているかを確認し、自動的に税額計算に反映してくれます。
住宅用地の特例についても同様です。
ただし、万が一、届いた納税通知書を見て軽減措置が適用されていないと思われる場合は、すぐに納税通知書に記載されている市区町村の資産税課などの担当窓口に問い合わせてみましょう。
はい、承知いたしました。前回の続きから本文を生成します。
新築・中古・戸建てによる固定資産税の違いを比較
「どの物件タイプを選ぶかで、税金も変わるの?」という点は、物件選びの重要なポイントです。
それぞれの税金の特徴を理解すれば、ご自身のライフプランに合った賢い物件選びができます。
- 新築マンションと中古マンションの税金はどう違う?
- マンションと戸建て、固定資産税が高いのはどっち?
- タワーマンションは高層階ほど固定資産税が高くなる
まずは、多くの方が悩む新築と中古の違いから見ていきましょう。
新築マンションと中古マンションの税金はどう違う?
新築マンションと中古マンションの固定資産税における最大の違いは、前章で解説した「新築建物の軽減措置」が適用されるかどうかです。
新築の場合は最初の5年間(または7年間)は税金の優遇を受けられますが、中古マンションにはそのメリットがありません。
一方で、中古マンションは既に建築から年数が経っているため、建物の評価額そのものが新築時よりも低くなっています。
そのため、軽減措置がなくても、そもそもの税額が新築の6年目以降の税額より安いケースが多く見られます。
ただし、人気のエリアにある中古マンションは、土地の評価額が購入時から下がらない、あるいは上昇していることもあります。
その場合は思ったほど税金が安くならない可能性もあるため、注意が必要です。
| 税金面でのメリット | 税金面でのデメリット | |
| 新築マンション | ・建物の固定資産税が最初の5年間(または7年間)半分になる | ・軽減措置終了後に税額が上がる ・建物評価額が高いため、そもそもの税額は高め |
| 中古マンション | ・建物評価額が低く、そもそもの税額が安い傾向にある | ・新築の軽減措置は受けられない ・土地の評価額が下がりにくい場合は負担感が大きいことも |
マンションと戸建て、固定資産税が高いのはどっち?
「マンションと戸建て、どちらの固定資産税が高いか」は、「土地は戸建て」「建物はマンション」が高くなると覚えるのが分かりやすいです。
- 土地の税金:土地全体を単独で所有する戸建ての方が、全戸で土地を共有し一戸あたりの持ち分が小さいマンションより高くなる傾向です。
- 建物の税金:木造の戸建てに比べ、頑丈な鉄筋コンクリート造のマンションは資産価値が下がりにくいため、税金は高くなりがちで、下がりにくいのが特徴です。
このため、購入当初は戸建ての税金が高く、年数が経つにつれて建物の価値が大きく下がる戸建ての方が、マンションよりも税負担が軽くなる傾向にあります。
タワーマンションは高層階ほど固定資産税が高くなる
近年人気のタワーマンション(一般的に高さ60mを超えるマンション)ですが、その固定資産税には特有のルールがあることをご存知でしょうか。
2017年度の税制改正により、2018年以降に引き渡された新築のタワーマンションでは、同じ広さの部屋でも階数によって固定資産税額が変わるように調整されています。
具体的には、マンション全体の建物の固定資産税額を、各部屋に割り振る際に階数に応じて傾斜をつけます。
一般的に、中層階がそのマンションの平均的な税額となり、それより高層階は税額が少し高く、低層階は税額が少し安くなる仕組みです。
これは、同じマンション内でも高層階ほど市場での売買価格が高いという実態を反映し、税負担の公平性を確保するために導入されました。
これからタワーマンションの購入を検討する方は、希望する部屋の階数によって将来の固定資産税が変わる可能性があることを覚えておきましょう。
マンションの固定資産税はいつ・どうやって支払う?納税の流れと注意点
「税金の支払い、うっかり忘れてしまったらどうしよう…」と不安に感じる方もいるでしょう。
納税の年間の流れと多彩な支払い方法を知っておけば、もう慌てることはありません。
- 納税通知書は毎年いつ頃届く?
- 支払い方法一覧(口座振替・クレジットカードなど)
- もし固定資産税を滞納するとどうなるのか
まずは、納税のスタート地点である「納税通知書」がいつ届くのかを確認しましょう。
納税通知書は毎年いつ頃届く?
マンションの固定資産税は、お住まいの市区町村から郵送されてくる「納税通知書」を使って納付します。
この通知書は、その年の1月1日時点でのマンションの所有者宛てに送付されます。
送付される時期は自治体によって異なりますが、一般的には毎年4月~6月頃に届くことが多いです。
例えば、東京23区の場合は毎年6月上旬に発送されます。
納税通知書には、税額の内訳がわかる「課税明細書」と、実際に支払いを行うための「納付書」が同封されています。支払いは年4回に分割して納めるのが基本で、それぞれの納付期限は以下のようになっています。
- 第1期:6月末
- 第2期:9月末
- 第3期:12月末
- 第4期:翌年2月末
※上記は一般的な例です。納付期限は自治体によって異なりますので、必ずご自身の納税通知書で正確な日付を確認してください。
もちろん、第1期の納付期限までに4期分すべてをまとめて支払う「全期前納(一括払い)」も可能です。
支払い方法一覧(口座振替・クレジットカードなど)
固定資産税の支払い方法には、金融機関やコンビニの窓口で現金で支払う以外にも、便利な選択肢が多数用意されています。
ご自身のライフスタイルに合った方法を選びましょう。
| 支払い方法 | メリット | デメリット・注意点 |
| 現金払い (金融機関・コンビニ等) |
・手数料がかからない ・その場で領収書がもらえる |
・窓口まで行く手間と時間がかかる ・高額な現金の持ち運びが必要な場合がある |
| 口座振替 | ・一度手続きすれば自動で引き落とされるため、払い忘れの心配がない | ・事前に金融機関での申し込みが必要 ・引き落とし日当日に口座残高が不足しないよう注意が必要 |
| クレジットカード払い | ・カード会社のポイントが貯まる ・自宅で24時間いつでも支払える |
・自治体によっては決済手数料がかかる場合がある ・領収書は発行されない(カードの利用明細で確認) |
| スマホ決済アプリ (PayPay, LINE Pay等) |
・自宅のソファからでも手軽に支払える ・キャンペーン等でポイント還元があることも |
・アプリによっては支払い上限額が設定されている ・領収書は発行されない(アプリの履歴で確認) |
近年、クレジットカード払いやスマホ決済に対応する自治体は急速に増えています。
ただし、どの支払い方法が利用できるかは自治体によって異なりますので、まずはお住まいの市区町村のウェブサイトなどで確認することをおすすめします。
もし固定資産税を滞納するとどうなるのか
万が一、納付期限までに固定資産税を支払うのを忘れてしまった場合、法律に基づいて段階的に手続きが進められます。
まず、納付期限の翌日から「延滞金」が発生します。
延滞金の利率は決して低くはなく、滞納した日数が長くなるほど負担は雪だるま式に増えていきます。
納付期限から約20日を過ぎても支払いがない場合、自治体から「督促状」が郵送されてきます。
これは「税金を早く納めてください」という最終勧告です。
そして、この督促状さえも無視し続けてしまうと、最終的には給与や預貯金、生命保険、そして最悪の場合、所有しているマンションそのものといった財産が強制的に差し押さえられる可能性があります。
これは法律に基づく強制的な手続きであり、決して他人事ではありません。
支払いが困難な特別な事情がある場合は、放置せずにできるだけ早く市区町村の納税課などの窓口に相談することが非常に重要です。
分割納付などの相談に応じてくれる場合もあります。
マンションの固定資産税でよくある質問
「一通り理解したつもりでも、まだ細かい疑問が残っている…」という方もいるでしょう。
ここでは、皆さんが特に気になる質問をQ&A形式でまとめました。ぜひ最後の疑問解消にお役立てください。
- 納税通知書のどこを見ればいいですか?
- 固定資産税がかからないケースはありますか?
- 古い中古マンション(築30年など)の購入は後悔しますか?
- 固定資産税はいつまで払い続けるのですか?
まずは、毎年届く納税通知書のチェックポイントからです。
Q. 納税通知書のどこを見ればいいですか?
A:納税通知書が届いたら、主に以下の4つのポイントを確認しましょう。専門用語が多くて難しく感じますが、ポイントを絞れば大丈夫です。
- 物件情報
「所在」や「家屋番号」などの欄を見て、課税対象となっている物件がご自身の所有するマンションと一致しているかをまず確認します。 - 価格(=固定資産税評価額)
「価格」または「評価額」と記載されている欄の金額が、税額計算の基礎となる最も重要な数字です。土地と建物のそれぞれに記載されています。 - 課税標準額
「課税標準額」の欄は必ずチェックしてください。特に土地の課税標準額が「価格」よりも大幅に低い金額(6分の1程度)になっていれば、住宅用地の特例が正しく適用されている証拠です。 - 税相当額
最終的にあなたが支払う税額が記載されている部分です。固定資産税と都市計画税の内訳もここで確認できます。
これらのポイントを押さえることで、ご自身の税額がどのように算出されたのかを理解でき、納得して納税することができます。
Q. 固定資産税がかからないケースはありますか
A:結論から言うと、理論上はかからないケースもありますが、現実的にはほぼありません。
固定資産税には「免税点」という制度があります。これは、同一の市区町村内に所有する資産の課税標準額の合計が、以下の金額に満たない場合には課税されないというものです。
- 土地:30万円未満
- 家屋(建物):20万円未満
しかし、マンションの場合、土地と建物の評価額の合計がこの免税点を下回ることは、まず考えられません。
そのため、実質的には「マンションを所有している限り、固定資産税は必ずかかる」と考えておくのが正解です。
Q. 古い中古マンション(築30年など)の購入は後悔しますか?
A:固定資産税の観点だけで見れば、築30年といった古いマンションは建物の評価額がかなり下がっているため、税負担は軽い傾向にあります。
しかし、「後悔しないか」という問いに対しては、税金以外の視点が非常に重要になります。
特に注意すべきなのは、固定資産税以外のランニングコストである「管理費」と「修繕積立金」です。
古いマンションほど大規模な修繕工事が必要になるため、修繕積立金が将来大幅に値上がりしたり、一時金を徴収されたりするリスクがあります。
また、建物の耐震性(1981年に導入された新耐震基準を満たしているか)や、水回りなどの設備の老朽化も重要なチェックポイントです。
固定資産税の安さだけで判断するのではなく、これらの維持費や将来のリフォーム費用まで含めたトータルのコストと、建物の管理状態を総合的に見極めることが、後悔しない中古マンション選びの鍵となります。
Q. 固定資産税はいつまで払い続けるのですか?
A:固定資産税は、そのマンションを所有している限り、永続的に払い続ける必要があります。
多くの方が勘違いしがちなのですが、住宅ローンを完済しても、固定資産税の支払い義務がなくなるわけではありません。
建物がどれだけ古くなっても、資産としての価値がゼロにならない限りは課税対象であり続けます。
この支払い義務がなくなるのは、そのマンションを誰かに売却したり、相続で手放したりして、所有者でなくなった時だけです。
マンションを持つということは、この永続的な税負担も受け入れることになります。
購入を検討する際は、この点をしっかりと理解した上で、長期的な資金計画を立てることが大切です。
まとめ:固定資産税を理解して、安心のマンションライフを
この記事では、マンションの固定資産税について、その相場から具体的な計算方法、税金を安くする軽減措置、そして支払い方法に至るまで、あなたが損をしないための知識を網羅的に解説しました。
最後に、本記事の特に重要なポイントを振り返りましょう。
- 相場は年間10万~30万円が目安
実際の金額は立地や広さ、築年数で大きく変わります。ご自身の状況に近いシミュレーションを参考に、大まかな金額を把握しておくことが大切です。 - 税金を安くする鍵は「軽減措置」
特に「新築建物の軽減措置」と、土地に適用される「住宅用地の特例」は非常に強力です。これらの制度が自動的に適用されることを知っておくだけでも、安心感が違います。 - 将来の税額変動と永続性を忘れない
新築マンションは6年目に税額が上がること、そして固定資産税はマンションを所有している限り永続的に支払いが必要なコストであることを、資金計画に必ず含めておきましょう。
固定資産税は、一見すると複雑で難しく感じるかもしれません。
しかし、その仕組みやポイントを一度理解してしまえば、決して怖いものではなく、むしろ、ご自身の資産にかかるコストを正しく把握することで、安心して資金計画を立て、納得のいくマンション選びができるようになります。
もし具体的な物件の税額でわからないことがあれば、不動産会社の担当者や市区町村の資産税課に相談することも有効です。
正しい知識を味方につけて、安心で快適なマンションライフを実現させましょう。
AIで不動産査定!
AIがお持ちの不動産の市場相場を診断