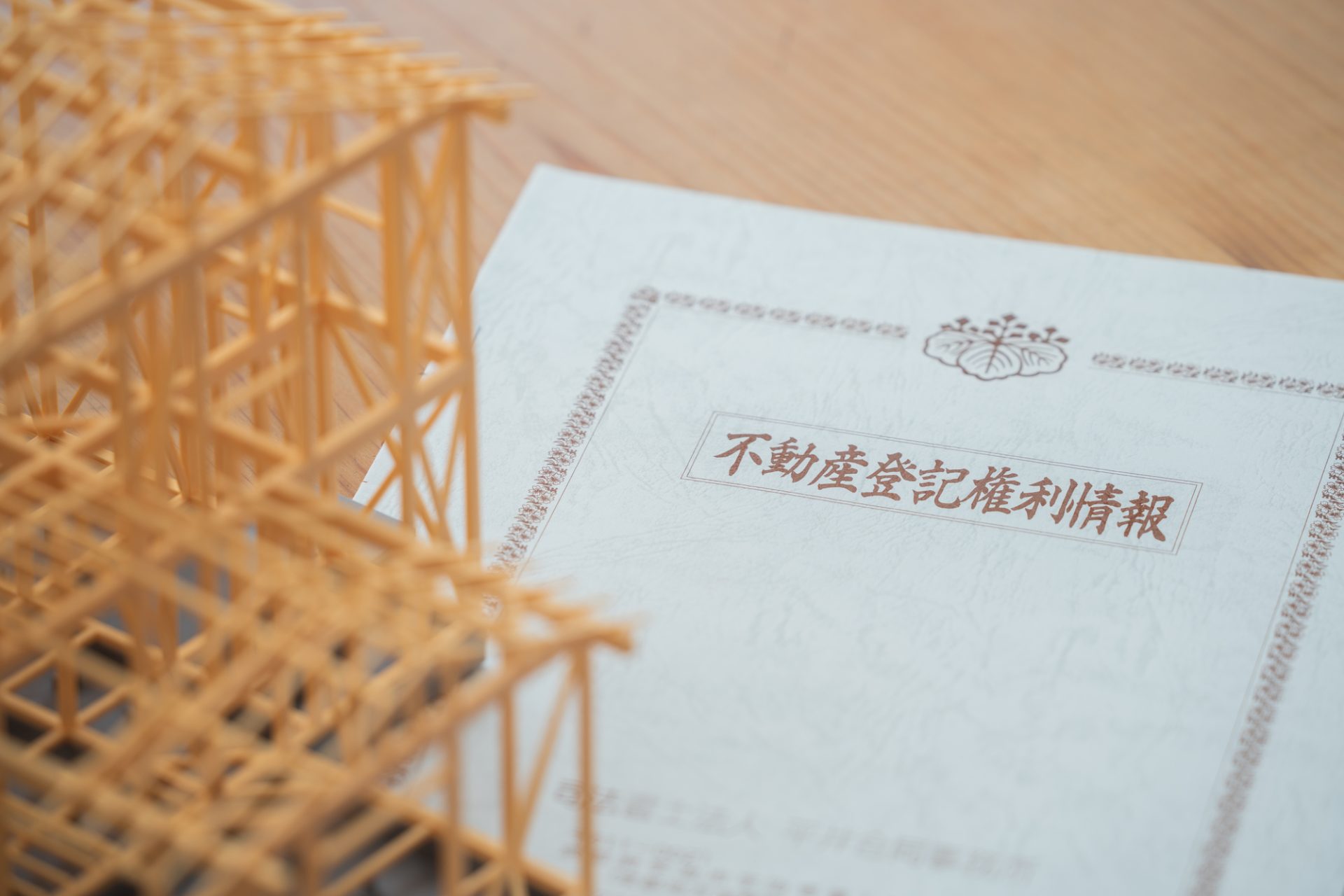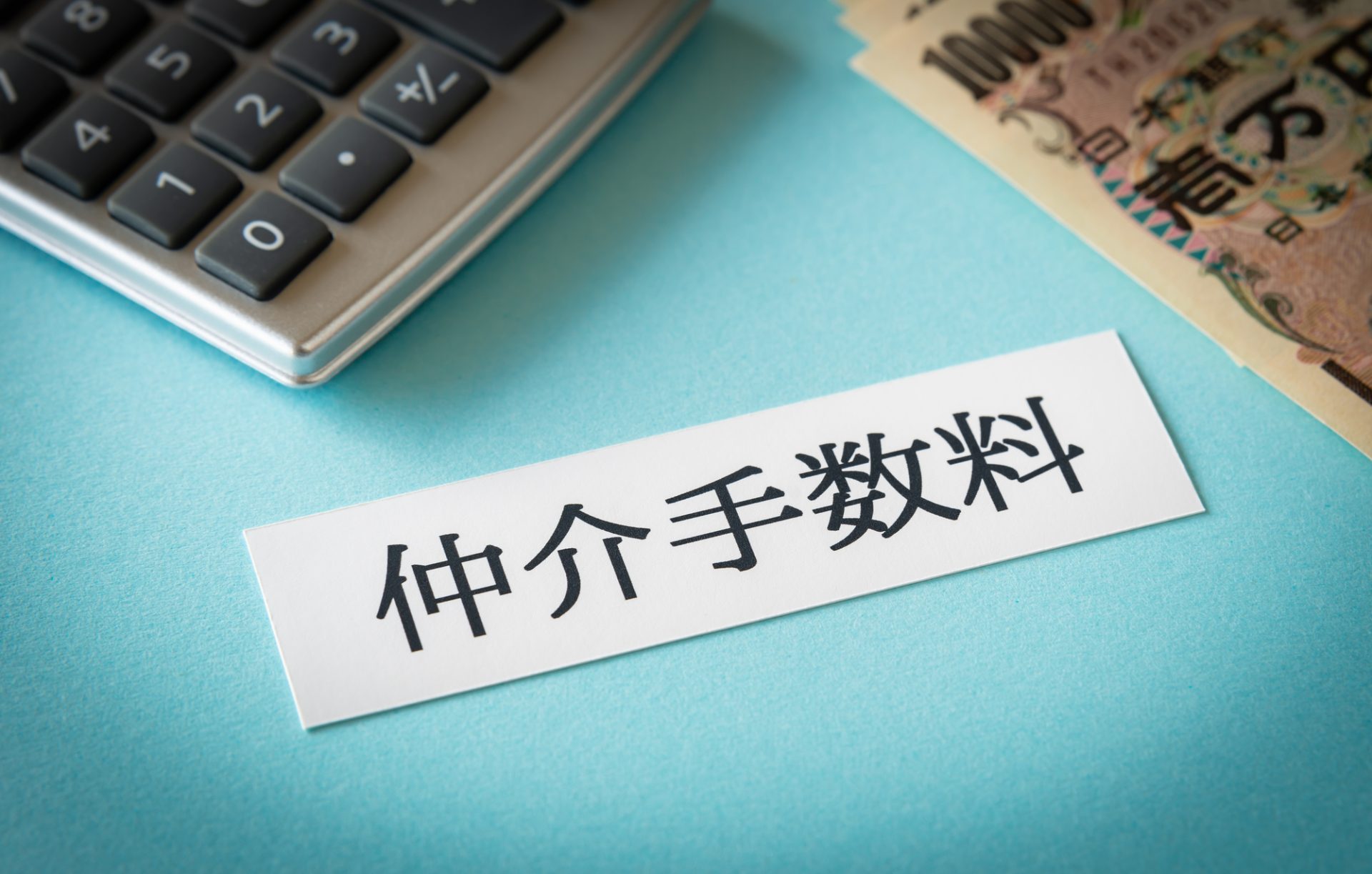「親から相続した実家、空き家のままだと固定資産税はどうなるの?」「税金が6倍になるって本当?」と、不安を抱えていませんか。
その不安を放置してしまうと、ある日突然、税金の優遇措置が打ち切られ、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。
しかし、ご安心ください。空き家の固定資産税が上がる仕組みを正しく理解し、ご自身の状況に合った対策を講じることで、その負担は大きく減らすことができます。実際に多くの方が、早めに知識を得て行動することで、余計な税金を払うことなく空き家問題を解決しています。
この記事では、固定資産税が上がる仕組みから、税金の負担を増やさないための具体的な「4つの対策」、さらには利用できる減免制度まで、専門家が分かりやすく解説します。
手遅れになる前に、この記事を読んで、あなたに最適な一歩を踏み出しましょう。
この記事のポイント
- 放置した空き家の固定資産税が最大6倍になる仕組みを解説
- 税金が上がる「特定空家」「管理不全空家」の具体的な状態がわかる
- 固定資産税の負担を増やさないための具体的な4つの対策を紹介
- 利用できる減免制度や困ったときの相談先がわかる
目次
空き家の固定資産税が6倍に?納税義務者と税金の仕組み
「税金が上がるって聞くけど、そもそも誰が払うの?」といった、基本的な疑問がありますよね。
この章では、納税義務者から税金が上がる仕組み、法改正のポイントまでを分かりやすく解説します。
- そもそも空き家の固定資産税は誰が払うのか?
- なぜ住んでいない家の固定資産税が高くなるのか
- 税金が割引される「住宅用地の特例」とは
- 2023年の法改正で「管理不全空家」も優遇対象外に
まずは、固定資産税の基本から理解していきましょう。
そもそも空き家の固定資産税は誰が払うのか?
空き家にかかる固定資産税を支払う義務があるのは、その年の1月1日時点での所有者です。
これは、法務局の登記簿に所有者として登録されている人を指します。
親から家を相続した場合、不動産の名義変更(相続登記)を行うと、新たな所有者となった相続人が納税義務者となります。
もし相続人が複数いる場合は、その全員が連帯して納税義務を負うことになり、代表者がまとめて支払うのが一般的。
たとえその家に住んでいなくても、所有者である限り納税の義務はなくならないため、誰が支払うのかを明確にしておくことが重要です。
なぜ住んでいない家の固定資産税が高くなるのか
住んでいない空き家なのに、なぜ固定資産税が高くなるのでしょうか。
結論から言うと、「税金が純粋に上がる」のではなく、「これまで適用されていた税金の割引が受けられなくなる」が正しい表現です。
通常、人が住むための家が建っている土地には、税金を安くする「住宅用地の特例」という制度が適用されています。
しかし、管理されずに放置された危険な空き家だと判断されると、この特例の対象から外されてしまいます。
その結果、割引がなくなった土地の固定資産税は本来の額に戻るため、支払う金額が最大で6倍にもなり、「税金が高くなった」と感じるのです。
税金が割引される「住宅用地の特例」とは
「住宅用地の特例」は、住宅地の税負担を軽減するための重要な制度です。
この特例によって、土地の固定資産税の基準となる課税標準額が大幅に引き下げられます。
具体的には、土地の広さに応じて以下の通り割引が適用されます。
| 区分 | 面積 | 固定資産税の課税標準 |
| 小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 価格の6分の1 |
| 一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 価格の3分の1 |
例えば、200㎡以下の土地であれば、固定資産税が6分の1にまで減額されていることになります。
この特例が適用されなくなると、税額が一気に跳ね上がることがお分かりいただけるでしょう。
2023年の法改正で「管理不全空家」も優遇対象外に
これまでは、特に危険な状態である「特定空家」に指定された場合のみ、この住宅用地の特例が解除されていました。
しかし、2023年12月に施行された「改正空家等対策特別措置法」により、状況はさらに厳しくなっています。
この法改正によって、「特定空家」になる手前の段階である「管理不全空家」も、行政からの指導・勧告に従わない場合は、特例解除の対象に含まれることになりました。
窓ガラスが割れていたり、雑草が生い茂っていたりするような状態でも、税金が上がるリスクが生じるのです。
これにより、固定資産税増額のリスクを負う空き家の対象が大きく広がったため、これまで以上に適切な管理が求められるようになりました。
この「管理不全空家」や、さらに深刻な「特定空家」がどのような状態を指すのか、そして、どのように税金が上がるプロセスを辿るのかは、法律で明確に定められています。
以下の国土交通省の公式サイトで、その法的な根拠を確認することができます。
【出典】 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
要注意!固定資産税が上がる「特定空家」「管理不全空家」とは
「特定空家」や「管理不全空家」って、具体的にどんな状態なのか気になりますよね。
ここでは、指定される基準や行政からの通知の流れなど、具体的な内容を解説します。
- この状態は危険信号!「特定空家」に指定される4つの基準
- 特定空家になる手前の「管理不全空家」とはどんな状態か
- 指導から勧告へ、固定資産税が上がるまでの流れ
ご自身の空き家が当てはまらないか、確認してみましょう。
この状態は危険信号!「特定空家」に指定される4つの基準
「特定空家」とは、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす、特に危険な状態の空き家を指します。法律では、以下の4つのいずれかに当てはまる状態と定められています。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
建物が傾いていたり、基礎や壁に大きな亀裂が入っていたりするなど、倒壊や建材の飛散の危険がある状態です。 - 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ゴミが放置され悪臭がする、ネズミや害虫が大量に発生しているなど、衛生環境を悪化させている状態を指します。 - 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
建物の外壁が落書きだらけであったり、窓ガラスが全て割れたまま放置されていたりするなど、地域の景観を大きく損ねている状態です。 - その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
庭の木が隣家や道路にまではみ出している、不審者が容易に侵入できるなど、周辺住民の生活に直接的な影響を及ぼしている状態を言います。
これらの基準は、一つでも当てはまれば「特定空家」と判断される可能性があります。
特定空家になる手前の「管理不全空家」とはどんな状態か
2023年の法改正で新たに加わったのが「管理不全空家」です。
これは、上記の「特定空家」になるのを未然に防ぐためのカテゴリーで、いわば特定空家の予備軍と言える状態を指します。
具体的には、以下のような状態が挙げられます。
- 窓ガラスが数枚割れている
- 外壁の一部が剥がれかけている
- 庭の雑草が伸び放題になっている
- 雨どいが壊れ、雨水が垂れ流しになっている
「特定空家」ほど深刻ではないものの、このまま放置すればいずれ特定空家になってしまう可能性が高い状態です。
この「管理不全空家」と判断された場合も、行政からの勧告に従わなければ固定資産税の優遇が受けられなくなるため、決して軽視はできません。
指導から勧告へ、固定資産税が上がるまでの流れ
所有する空き家が、いきなり「特定空家」や「管理不全空家」に指定されて、すぐに税金が上がるわけではありません。
行政は、法律に基づいて段階的に措置を進めていきます。
その流れを理解しておくことが非常に重要です。
| ステップ | 行政の対応 | 所有者への影響 |
| ステップ1:助言・指導 | 市町村が空き家の状態を調査し、所有者に対して適切な管理を促す「助言」や「指導」を行います。 | この段階では法的な強制力はなく、罰則もありません。 |
| ステップ2:勧告 | 指導に従わず、状態が改善されない場合に「勧告」が出されます。 | この勧告を受けると、住宅用地の特例が解除され、翌年から固定資産税が最大6倍になります。 |
| ステップ3:命令 | 勧告にも従わない場合、市町村は期限を定めて改善を「命令」します。 | 命令に違反すると、50万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。 |
| ステップ4:行政代執行 | 命令にも従わない最終手段として、行政が所有者に代わって解体などの措置を行います。 | 解体などにかかった費用は、すべて所有者に請求されます。 |
このように、税金が上がるのは「勧告」のタイミングです。
しかし、それ以前の「助言・指導」の段階で迅速に対応することが、経済的な負担を最小限に抑えるためのポイントとなります。
自分の空き家はいくら?固定資産税の計算方法とシミュレーション
「自分の空き家の場合、税金は具体的にいくらになるの?」と気になりますよね。
ここでは、税額の計算に必要な評価額の確認方法と、簡単なシミュレーションを解説します。
- まずは「固定資産税評価額」を確認する方法
- 簡単シミュレーション!空き家と更地の固定資産税を比較
具体的な税額のイメージを掴んでいきましょう。
まずは「固定資産税評価額」を確認する方法
固定資産税の税額を計算する上で、基本となるのが「固定資産税評価額」です。
これは、市町村が個別の土地や建物に対して決定する公的な価格で、3年に一度見直されます。
この評価額を確認する最も簡単な方法は、毎年4月〜6月頃に市町村から送られてくる固定資産税の「納税通知書」を見ることです。
納税通知書に同封されている「課税明細書」の中に、「価格」または「評価額」という欄があります。
そこに記載されている金額が、あなたの所有する土地と建物の固定資産税評価額です。
もし手元に書類がない場合は、空き家のある市町村の役所(資産税課など)で「固定資産評価証明書」を発行してもらうことで確認できます。
まずはこの評価額を把握することが、税額を知るための第一歩です。
簡単シミュレーション!空き家と更地の固定資産税を比較
では、実際にどれくらい税額が変わるのか、具体的なモデルケースで見ていきましょう。
【モデルケース】
- 土地の面積: 180㎡
- 土地の評価額: 1,800万円
- 建物の評価額: 600万円
- 固定資産税率: 1.4%(標準税率)
この空き家が、行政から「勧告」を受けた場合と受けなかった場合で、年間の固定資産税額がどう変わるのかを比較します。
| 項目 | ① 通常の空き家
(特例あり) |
② 勧告を受けた空き家
(特例なし) |
| 土地の固定資産税 | (1,800万円 × 1/6) × 1.4%
= 42,000円 |
1,800万円 × 1.4%
= 252,000円 |
| 建物の固定資産税 | 600万円 × 1.4%
= 84,000円 |
600万円 × 1.4%
= 84,000円 |
| 合計 | 126,000円 | 336,000円 |
| 年間の差額 | – | 210,000円 |
※上記は固定資産税のみの計算です。都市計画税(税率0.3%上限)が課される地域では、さらに負担が増加します。
このシミュレーションから分かるように、建物の税額は変わりませんが、土地の税額が6倍になっています。行政から「勧告」を受けるだけで、このケースでは年間の負担が21万円以上も増えてしまうのです。
このように具体的な数字で見ると、いかに「住宅用地の特例」が大きな役割を果たしているか、そしてそれを失う影響が大きいかがお分かりいただけると思います。
空き家の固定資産税を上げないために!今すぐできる具体的な対策
「税金が上がるのは困るけど、具体的にどうすればいいの?」と悩みますよね。
この章では、固定資産税の負担を増やさないための4つの具体的な対策を解説します。
- 適切に管理して固定資産税の優遇を維持する
- 売却して固定資産税の負担とリスクをなくす
- 賃貸や活用で収益を生む資産に変える
- 解体のメリットと固定資産税に関する注意点
あなたに合った方法を見つけていきましょう。
適切に管理して固定資産税の優遇を維持する
最も基本的かつ重要な対策は、空き家を適切に管理し続けることです。「特定空家」や「管理不全空家」に指定されさえしなければ、固定資産税の優遇(住宅用地の特例)は継続して受けられます。
具体的には、以下のような管理を定期的に行うことが求められます。
- 室内の換気と清掃
- 庭の草むしりや樹木の剪定
- 郵便受けの整理
- 破損箇所(割れた窓や雨どいなど)の修繕
もし遠方に住んでいてご自身での管理が難しい場合は、専門の「空き家管理サービス」を利用するのも有効な選択肢です。月々数千円から一万円程度の費用はかかりますが、税金が何十万円も上がるリスクや、建物の劣化を防ぐことを考えれば、十分に価値のある投資と言えるでしょう。
売却して固定資産税の負担とリスクをなくす
今後その空き家を利用する予定がなく、管理の手間や費用を負担に感じる場合は、「売却」が最も確実な解決策となります。
売却してしまえば、翌年からの固定資産税の支払いはもちろん、火災や倒壊といった将来的なリスク、そして何より管理の手間から完全に解放されます。売却方法には、建物を残したまま「古家付き土地」として売る方法と、建物を「解体して更地」で売る方法があります。
また、相続した空き家を売却する際には、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」という税金の優遇制度が使える可能性があります。
これは、売却によって得た利益から最大3,000万円を差し引けるという非常に大きな制度です。適用には条件があるため、まずは不動産会社に相談してみることをお勧めします。
この「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」は非常に強力な制度ですが、適用にはいくつかの条件があります。
ご自身のケースが当てはまるか、以下のチェックリストで確認してみましょう。
【かんたんチェック】3,000万円特別控除は使える?
- 親など(被相続人)から相続した家である
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家である
- 相続してから売却まで、事業や賃貸に使っていない
- 売却代金が1億円以下である
- 売却するのが、相続開始から3年後の年末までである
上記は主な要件です。より詳しい条件や手続きについては、国土交通省の以下のページが図解付きで分かりやすく解説しています。
【出典】 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」
賃貸や活用で収益を生む資産に変える

【参照】 国土交通省「全国版空き家・空き地バンク」の本格運用を開始
「家自体は手放したくない」「誰かに使ってほしい」という想いがあるなら、空き家を収益資産に変える活用方法を検討してみましょう。
適切に活用すれば、固定資産税を支払うどころか、プラスの収入を生み出すことも可能です。
主な活用方法としては、以下のようなものが挙げられます。
- 賃貸物件として貸し出す: リフォームが必要な場合もありますが、安定した家賃収入が期待できます。
- 民泊として活用する: 観光地などの立地が良ければ、高い収益性が見込めます。
- 空き家バンクに登録する: 自治体を介して、移住希望者などに貸し出したり売却したりする制度です。
これらの方法は、空き家が負債から資産へと変わる魅力的な選択肢ですが、初期投資や運営の手間がかかることも事実です。
ご自身の労力やかけられる費用を考慮して、慎重に検討することが大切になります。
解体のメリットと固定資産税に関する注意点
建物の老朽化が著しく、活用も売却も難しい場合の最終手段が「解体」です。
建物を解体すれば、倒壊や火災のリスク、不審者の侵入といった保安上の問題がなくなり、維持管理の負担からも解放されるという大きなメリットがあります。
しかし、解体には非常に重要な注意点が存在します。それは、建物を解体して更地にすると、「住宅用地の特例」が適用されなくなるという点です。つまり、翌年から土地の固定資産税は割引のない本来の額に戻り、今よりも高くなってしまいます。
また、百万円単位の解体費用も必要です。そのため、解体は「更地にしてすぐに売却する」「駐車場として活用する」など、その後の土地活用の計画が明確な場合にのみ選択すべき方法と言えるでしょう。
もしかして安くなる?空き家の固定資産税の減免制度について
「何か税金が安くなる制度はないの?」と、少しでも負担を減らしたいですよね。
ここでは、条件に合えば利用できる固定資産税の減免制度と、その手続きを解説します。
- 災害などの特別な場合に受けられる減免措置
- 自治体独自の減免制度(条例)を確認する方法
- 減免を受けるための申請手続きの流れ
あなたが対象になるか、確認してみましょう。
災害などの特別な場合に受けられる減免措置
固定資産税には、納税が困難な特別な事情がある場合に、税負担を軽くする「減免制度」が設けられています。
これは、主に以下のようなケースが対象となります。
- 災害による被害
地震、台風、火災などによって建物が全壊・半壊したり、大きな被害を受けたりした場合。被害の程度に応じて、税額が全額免除または一部減額されます。 - 生活困窮
生活保護を受けているなど、経済的な理由で納税が著しく困難な場合。 - 公益のための利用
所有する空き家を、地域の集会所やNPO法人の活動拠点といった公共の目的のために無償で提供している場合。
これらの減免は、法律で定められた基本的なものであり、適用されるケースは限定的です。しかし、万が一の際には非常に重要な制度となります。
自治体独自の減免制度(条例)を確認する方法
国の定める基本的な制度とは別に、各市町村が条例によって独自の減免制度を設けていることがあります。空き家問題の解決を促進するため、ユニークな制度を用意している自治体も少なくありません。
例えば、以下のような制度が考えられます。
- 自治体が運営する「空き家バンク」に物件を登録し、成約した場合
- 子育て世帯や移住者に空き家を貸し出した場合
- 歴史的価値のある建物の保存活用に取り組む場合
これらの制度は自治体によって内容が大きく異なるため、まずはご自身の空き家がある市町村の情報を確認することが重要です。役所のウェブサイトで「固定資産税 減免」と検索したり、資産税課や空き家対策の担当課に直接問い合わせたりしてみましょう。
減免を受けるための申請手続きの流れ
減免制度の最も重要なポイントは、自動的に適用されるのではなく、必ず所有者自身による申請が必要だということです。待っているだけでは、税金は安くなりません。
一般的な手続きの流れは以下の通りです。
- 事前相談と要件確認
まずは役所の担当窓口に連絡し、自分が減免の対象となるか、どのような書類が必要かを確認します。 - 申請書の作成
役所の窓口やウェブサイトで申請書を入手し、必要事項を記入します。 - 必要書類の準備
減免の理由を証明する書類(例:罹災証明書、賃貸借契約書のコピーなど)を用意します。 - 期限内に提出
作成した申請書と必要書類を、必ず納期限までに役所に提出します。納期限を1日でも過ぎると、その年度の申請を受け付けてもらえない場合がほとんどなので、期限の確認は非常に重要です。
提出後、自治体による審査が行われ、後日、減免が認められるかどうかの決定通知が届きます。手続きの詳細は自治体によって異なるため、必ず事前に担当窓口へ確認するようにしてください。
空き家の固定資産税で困ったときの相談先まとめ
「色々考えたけど、一人で決めるのは不安…」どこに相談すればいいか迷いますよね。
最後に、あなたの悩みに合わせて相談できる専門の窓口を3つご紹介します。
- まずは市町村の役所の相談窓口へ
- 売却や活用なら地域の不動産会社に相談
- 空き家問題の専門家であるNPO法人も選択肢に
専門家の力を借りて、問題を解決しましょう。
まずは市町村の役所の相談窓口へ
何から手をつけていいか全く分からない、という場合に、最初の相談先として最もおすすめなのが、空き家のある市町村の役所です。
資産税課、都市計画課、空き家対策担当課といった部署が相談窓口となっており、総合案内で聞けば担当につないでくれます。公的な機関なので、無料で安心して相談できるのが最大のメリットです。
役所では、固定資産税の詳細や減免制度についてはもちろん、自治体独自の補助金制度や、提携している専門家(司法書士や建築士など)を紹介してもらえる場合もあります。まずはここで全体像を把握することから始めましょう。
売却や活用なら地域の不動産会社に相談
空き家の売却や賃貸を具体的に検討しているなら、地域の事情に詳しい不動産会社への相談が欠かせません。
不動産会社に相談すれば、あなたの空き家が「いくらで売れるのか」「いくらで貸せるのか」といった具体的な査定額を知ることができます。さらに、その地域の需要に基づいた最適な売却戦略や活用方法を提案してもらえるでしょう。
相続した空き家を売る際の「3,000万円特別控除」といった税金の優遇措置についても、専門的なアドバイスが期待できます。一社だけでなく、複数の会社に相談して、最も信頼できるパートナーを見つけることが大切です。
空き家問題の専門家であるNPO法人も選択肢に
近年、空き家問題の解決を専門にサポートするNPO法人や一般社団法人といった団体も増えています。
これらの団体は営利を目的としないため、売却や解体を急かすことなく、所有者の気持ちに寄り添った中立的な立場でアドバイスをくれるのが特徴です。賃貸や売却だけでなく、地域のコミュニティスペースへの活用やDIY型賃貸など、行政や不動産会社とは違ったユニークな活用ノウハウを持っている場合もあります。
「(自治体名) 空き家 NPO」などで検索すると、お住まいの地域で活動している団体が見つかるかもしれません。第三者の客観的な意見を聞きたい場合に、心強い味方となってくれるでしょう。
まとめ:空き家問題は早めの対策と相談が鍵
今回は、空き家の固定資産税が上がる仕組みから、具体的な対策、そして相談先までを詳しく解説しました。
空き家を放置してしまうと、固定資産税が最大6倍になるだけでなく、建物の倒壊や景観の悪化など、様々なリスクを生み出してしまいます。しかし、その仕組みを正しく理解し、
- 適切に管理する
- 売却する
- 活用する
- 解体する
といった選択肢の中から、ご自身の状況に合った最適な一手を選べば、問題は必ず解決できます。
大切なのは、一人で抱え込まず、手遅れになる前に専門家へ相談することです。この記事が、あなたが最初の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
AIで不動産査定!
AIがお持ちの不動産の市場相場を診断