
「そろそろ家を売りたいけど、一体いくらで売れるんだろう?」「不動産会社に相談する前に、まずは自分で相場を知っておきたい」そうお考えではありませんか。
相場を知らないまま話を進めてしまうと、気づかぬうちに本来の価値よりも低い価格で売却してしまうことにもなりかねません。
しかし、ご安心ください。実は、国が公表している信頼性の高いデータを活用すれば、誰でも無料で家の売却相場を調べることが可能です。
大切なのは、複数の価格指標を正しく理解し、総合的に判断することにあります。
この記事では、ご自宅の売却相場を自分で調べるための具体的な4つの方法から、価格が決まる仕組み、築年数や手数料に関する注意点まで、専門知識がなくても分かるように丁寧に解説します。
この記事のポイント
- 公的なデータを使い、自分で売却相場を調べる4つの方法が分かる
- 「実勢価格」や「公示地価」など、様々な不動産価格の違いを理解できる
- 「古い家」の価値がどう決まるのか、売却時の考え方が分かる
- 売却時にかかる仲介手数料の相場と計算方法が分かる
目次
なぜ価格が違う?売却時に知っておきたい3つの「不動産価格」

相場を調べると、いろいろな価格があって混乱しますよね。
それぞれの価格が持つ意味を知れば、相場をより正確に理解できるようになります。
ここでは、特に重要な以下の3つの価格について解説します。
- 実勢価格:実際に市場で取引される価格
- 公示地価:国が示す土地価格の目安
- 相続税路線価:相続税の基準となる土地価格
3つの価格の違いを、ここでしっかり整理していきましょう。
実勢価格:実際に市場で取引される価格
実勢価格とは、実際に市場で買主と売主の間で取引が成立した価格のことで、「時価」とも呼ばれます。
「不動産情報ライブラリ」で確認できる過去の取引事例は、この実勢価格にあたり、不動産の価格は、株式市場のように需要と供給のバランスによって常に変動しています。
周辺で新しい駅が開業すれば価格が上昇する傾向にありますし、近隣で同条件の物件が多く売りに出されれば価格競争が起こるかもしれません。
このように、様々な社会情勢や市場の動向を反映した、”生きた価格”が実勢価格です。
不動産会社に査定を依頼すると提示される「査定価格」は、この実勢価格の動向を基に「今売り出したら、3ヶ月以内にこのくらいの価格で売れるだろう」とプロが予測した価格ということになります。
公示地価:国が示す土地価格の目安
公示地価(こうじちか)は、国土交通省が毎年1月1日時点における全国の標準的な地点(標準地)の価格を判定し、3月に公表するものです。
これは、土地の適正な価格を知るための公的な指標であり、公共事業用地の取得価格を算定する際の基準にもなっています。
重要なのは、公示地価はあくまで土地のみの価格であり、建物の価値は含まれていない点です。そのため、公示地価だけを見て「自分の家もこの値段で売れる」と判断することはできません。
一般的に、実際の取引価格である実勢価格は、この公示地価の1.1倍〜1.2倍程度になることが多いと言われていますが、あくまで目安の一つとして捉えましょう。
相続税路線価:相続税の基準となる土地価格

相続税路線価(そうぞくぜいろせんか)は、その名の通り、相続税や贈与税を計算する際に基準となる土地の価格です。国税庁が毎年7月頃に、その年の1月1日時点の価格として公表します。
路線価は、主要な道路に面した土地1平方メートルあたりの価格で示されており、国税庁のウェブサイト「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認できます。
この相続税路線価は、先ほど説明した公示地価と連動しており、公示地価の8割程度の水準になるように設定されています。売却価格そのものではありませんが、土地の公的な評価額を知るための信頼できる指標です。
これら3つの価格の関係をまとめると、以下のようになります。
| 価格の種類 | 決定機関 | 目的・用途 | 公表時期 |
| 実勢価格 | 市場(需要と供給) | 実際の不動産取引 | — |
| 公示地価 | 国土交通省 | 公的な土地評価の指標 | 毎年3月 |
| 相続税路線価 | 国税庁 | 相続税・贈与税の算定 | 毎年7月 |
あなたの家の価値は?相場に影響を与える7つの重要ポイント

家の価格が一体どのような要素で決まるのか、気になりますよね。
売却相場に影響するポイントを知ることで、ご自宅の価値を客観的に把握できます。
ここでは、特に重要な以下の7つのポイントをご紹介します。
- 立地(駅からの距離・周辺環境)
- 築年数と建物の状態
- 土地と建物の広さ・間取り
- 土地の形と方角
- 接している道路の状況
- 都市計画(用途地域など)
- 災害リスク(ハザードマップ)
7つのポイントを順に確認し、ご自身の家に当てはめて考えてみましょう。
立地(駅からの距離・周辺環境)
不動産の価値を決定づける最も重要な要素が「立地」です。「不動産は立地がすべて」と言われるほど、その場所の利便性や住環境が価格に大きく反映されます。
特に重視されるのが最寄り駅からの距離で、一般的に「徒歩10分以内」が人気の目安。
また、スーパーマーケットやコンビニ、学校、病院、公園といった生活関連施設が周辺に充実しているかどうかも、暮らしやすさに直結するため重要な評価ポイントになります。
築年数と建物の状態
土地と異なり、建物は時間とともに劣化していくため、築年数が経過するほど価値は減少していきます。
特に木造戸建ての場合、税法上の法定耐用年数が22年とされていることから、築20年~25年を超えると建物の資産価値はゼロに近いと評価されるケースも少なくありません。
ただし、これはあくまで一般的な目安です。実際には、定期的なメンテナンスやリフォームが適切に行われているか、雨漏りやシロアリの被害といった瑕疵(かし)がないかなど、建物の個別の状態が価値を大きく左右します。
土地と建物の広さ・間取り
価格の基礎となるのが、土地面積と建物の延床面積です。当然ながら、面積が広いほうが高価格になります。
また、同じ延床面積であっても、間取りは評価に影響を与えます。
例えば、そのエリアの主な居住者層がファミリー層であれば、極端に部屋数が少ない間取りよりも、3LDK~4LDKといった需要の高い間取りの方が買い手を見つけやすく、有利な価格で売却できる可能性が高まります。
土地の形と方角
土地の使いやすさを左右する「形」と「方角」も、価格に影響するポイントです。
土地の形は、正方形や長方形といった凹凸のない「整形地」が最も評価が高くなります。敷地を有効に活用して建物を設計しやすいためです。
一方で、三角形の土地や、道路までの通路が細長い「旗竿地」などは、利用に制約があるため評価が下がる傾向にあります。
また、日当たりの良さは居住の快適性に直結するため、一般的に南向きの土地や、南側に道路が面している物件は人気が高く、価格も高めに設定されます。
接している道路の状況
意外と見落としがちですが、敷地が接している道路の状況も重要な評価ポイントです。
建築基準法では、建物を建てる敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という接道義務が定められています。
この条件を満たさない土地は、原則として建物の建て替えができない「再建築不可物件」となり、資産価値が大幅に下がってしまいます。
また、道路の幅(自動車の出し入れのしやすさ)や、公道か私道か、複数の道路に面した「角地」か(角地は評価が高い)といった点も価格を左右します。
都市計画(用途地域など)
不動産が所在するエリアは、「都市計画法」に基づいて「用途地域」が定められています。
用途地域とは、その地域に建てられる建物の種類や大きさ、高さなどを制限するルールです。
例えば、「第一種低層住居専用地域」は、低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、店舗や事務所を建てることは厳しく制限されます。
一方で「商業地域」では、様々な商業施設や高層マンションを建てることが可能です。
このように、ご自身の家がどの用途地域に属しているかによって、土地の活用方法や将来性が変わるため、評価額にも影響します。
災害リスク(ハザードマップ)
近年、自然災害への意識の高まりから、不動産取引において災害リスクがより重視されるようになっています。
国土交通省や各自治体が公表している「ハザードマップ」を確認し、ご自身の家が以下の区域に指定されていないかを確認することが重要です。
- 洪水浸水想定区域
- 土砂災害警戒区域
- 津波災害警戒区域
2020年の法改正により、不動産会社は売買契約の際に、取引する物件がハザードマップ上のどこに位置するかを説明することが義務付けられました。
災害リスクの有無は、買主の購入判断や金融機関の融資審査にも影響を与える可能性があります。
「古い家」は安くなる?築年数が売却相場に与える影響

ご自宅の築年数が古いと、いくらで売れるのか、そもそも売れるのかどうか不安ですよね。
しかし、築年数が経った家ならではの売却戦略を知れば、有利に売却を進めることが可能です。
ここでは、古い家の価値がどう見られるのか、そしてどのような売り方があるのかを解説します。
- 築20年超で建物価値はゼロ?木造戸建ての評価の仕組み
- 【築40年・50年】「古家付き土地」として売る戦略
- 解体して更地にするメリット・デメリット
- 売る前の大規模リフォームは基本的に不要な理由
古い家の価値と、それに合わせた最適な売り方を一緒に見ていきましょう。
築20年超で建物価値はゼロ?木造戸建ての評価の仕組み
「木造戸建ては築20年で価値がゼロになる」という話を聞いたことがあるかもしれません。
これは、税金の計算で使われる法定耐用年数(木造住宅の場合は22年)が根拠となっています。
この年数を超えると、税務上の建物の資産価値はほぼゼロとして扱われます。
もちろん、これは実際の建物の寿命や取引価格と完全に一致するわけではありません。
不動産市場においても、築20年~25年を境に建物の評価額は大きく下がり、売却価格の大部分を土地の価格が占めるようになるのが一般的です。
ただし、適切なメンテナンスが施されていて状態が良好な建物や、デザイン性の高い古民家などは、築年数が古くても価値が認められるケースもあります。
【築40年・50年】「古家付き土地」として売る戦略
築40年や50年といった築年数がかなり経過した物件の場合、買主の多くは「建物をそのまま使う」というより、「自由にリノベーションできる素材」または「新築を建てるための土地」として物件を探しています。
このような物件を売却する際に有効なのが、「古家(ふるや)付き土地」として売り出す戦略。
これは、あくまでメインは土地であり、建物は”おまけ”です、というスタンスで売却する方法です。
「古家付き土地」で売るメリット
- 買主が住宅ローンを使いやすい:更地の場合、建物プランが決まっていないと住宅ローンが組めないことがありますが、建物があればローン審査が通りやすくなります。
- 売主の費用負担がない:売主が事前に建物を解体する必要がないため、数百万円かかることもある解体費用を負担せずに済みます。
- 固定資産税を抑えられる:建物が建っていることで住宅用地の特例が適用され、更地よりも固定資産税が安いまま売却活動ができます。
解体して更地にするメリット・デメリット
もう一つの選択肢として、売主の負担で建物を解体し、「更地」として売却する方法もあります。それぞれのメリット・デメリットを理解しておきましょう。
| メリット | デメリット | |
| 更地にして売る | ・土地の広さや形が分かりやすく、買主が検討しやすい
・買主が解体費用を気にする必要がない ・地中の埋設物などのリスクを事前に確認できる場合がある |
・売主が100万円以上の解体費用を負担する必要がある
・固定資産税が最大6倍になる可能性がある ・解体費用を売却価格に上乗せできるとは限らない |
一般的には、買主のニーズがわからない段階で費用をかけて更地にするリスクは高いため、まずは「古家付き土地」として市場の反応を見るのが賢明な判断と言えるでしょう。
売る前の大規模リフォームは基本的に不要な理由
「少しでも高く売るために、リフォームした方が良いのでは?」と考える方も多いかもしれません。
しかし、結論から言うと、売却前の大規模なリフォームは基本的に不要です。
その理由は、リフォームにかけた費用をそのまま売却価格に上乗せできる保証がなく、費用倒れになるリスクが高いからです。
また、買主は自分たちの好みに合わせてリフォームやリノベーションをしたいと考えているケースが多く、良かれと思って行ったリフォームが、かえって敬遠される可能性すらあります。
ただし、雨漏りの補修や給湯器の修理といった最低限の修繕や、家全体の印象を良くするためのハウスクリーニング、不用品の処分などは、内覧時の印象を良くするために有効です。
家を売る時の仲介手数料はいくら?相場の計算方法と注意点
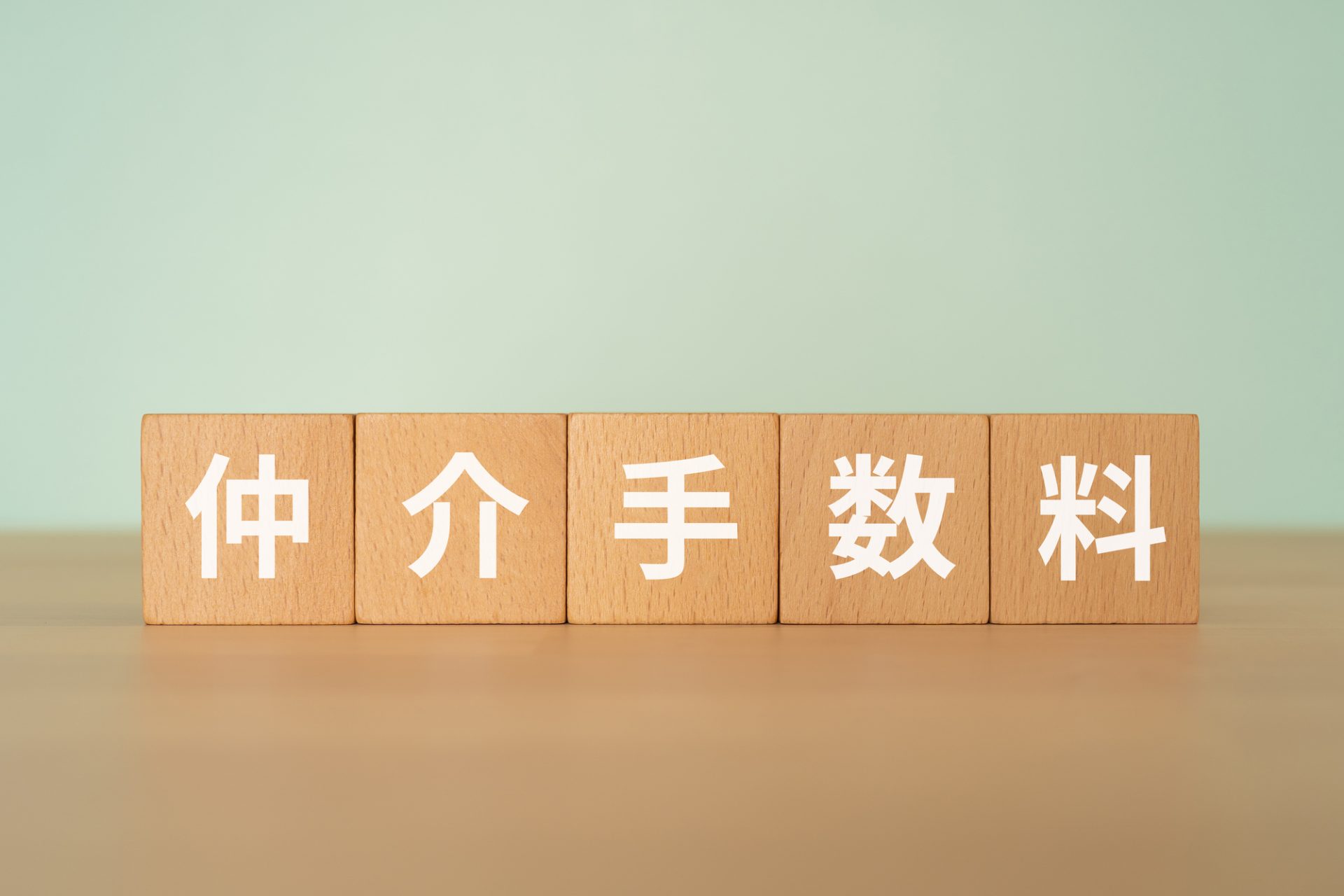
売却価格だけでなく、そこから引かれる手数料も気になりますよね。
仲介手数料の相場や計算方法を知っておけば、より具体的な資金計画を立てられます。
ここでは、売却にかかる費用について詳しく見ていきましょう。
- 法律で決まっている仲介手数料の上限額
- 速算式で簡単シミュレーション:売却価格3,000万円の場合
- 仲介手数料以外にもかかる諸費用一覧
ご自身のケースに当てはめて、費用がいくらになるか確認していきましょう。
法律で決まっている仲介手数料の上限額
不動産会社に支払う仲介手数料は、会社が自由に設定できるわけではなく、宅地建物取引業法によって上限額が定められています。
多くの不動産会社が、この上限額を正規の手数料として設定しています。
上限額は売却価格に応じて、以下の3段階の料率で計算されます。
| 売却価格の区分 | 料率(税抜) |
| 200万円以下の部分 | 5% |
| 200万円を超え400万円以下の部分 | 4% |
| 400万円を超える部分 | 3% |
例えば、家が1,000万円で売れた場合、200万円までの部分に5%、次の200万円(400万円-200万円)に4%、残りの600万円(1,000万円-400万円)に3%をそれぞれ掛けて合計額を算出します。
このように計算が複雑なため、一般的には次に紹介する「速算式」が用いられます。
速算式で簡単シミュレーション:売却価格3,000万円の場合
前述の複雑な計算を簡単にするため、売却価格が400万円を超える場合は、以下の速算式が広く使われています。
仲介手数料(税抜) = 売却価格 × 3% + 6万円
この式を使って、仮に家が3,000万円で売れた場合の仲介手数料をシミュレーションしてみましょう。
- 売却価格に3%を掛ける
¥30,000,000 × 3% = ¥900,000 - 6万円を足す
¥900,000 + ¥60,000 = ¥960,000(税抜手数料) - 消費税(10%)を加える
¥960,000 × 1.10 = ¥1,056,000(税込手数料)
このように、ご自身の売却希望価格を当てはめることで、仲介手数料のおおよその上限額を把握することができます。
仲介手数料以外にもかかる諸費用一覧
家の売却時には、仲介手数料が最も大きな費用となりますが、それ以外にもいくつか必要な諸費用があります。
代表的なものを知っておきましょう。
| 費用の種類 | 概要 | 目安 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼る印紙代。売却価格によって税額が変わる。 | 1万円~3万円 |
| 抵当権抹消登記費用 | 住宅ローンが残っている場合に、抵当権を抹消するための手続き費用。 | 1万円~5万円 |
| 譲渡所得税・住民税 | 家を売って利益(譲渡所得)が出た場合にのみかかる税金。 | 利益額による |
| その他 | 引っ越し費用、ハウスクリーニング代、測量費用など。 | ケースによる |
特に注意が必要なのが「譲渡所得税」です。これは売却して利益が出た場合にのみ課税される税金です。
マイホームの売却の場合は、利益から最高3,000万円を控除できる特例があるため、多くの場合、この税金はかかりません。
しかし、利益が3,000万円を超えるケースなどでは納税が必要になるため、覚えておきましょう。
より正確な価格を知るには「不動産査定」が不可欠な理由

これまでご自身で相場を調べる方法を見てきましたね。
しかし、ご自宅の本当の価値、つまり「現実的に売れるであろう価格」を知るには、プロの視点が欠かせません。
ここでは、なぜ不動産会社の査定が必要なのか、その理由を解説します。
- 自分で調べる相場の限界とは?
- 不動産会社は「個別の事情」を評価してくれる
- 複数の会社に査定を依頼する「一括査定」がおすすめ
ご自身の大切な資産の価値を、正しく見極めるためのステップに進みましょう。
自分で調べる相場の限界とは?
これまで紹介してきた公的データは、客観的な相場観(相場のおおよその感覚)を養う上で非常に強力なツールです。
しかし、それだけで正確な売却価格を導き出すことには限界があります。
その理由は、公的データが「過去」と「平均」の情報だからです。
不動産情報ライブラリのデータは過去の取引ですし、不動産価格指数はあくまで市場全体の平均的な動きです。現実の不動産市場は常に変動しており、また、一つとして同じ物件は存在しません。
日当たりの良さや室内の綺麗さ、リフォーム履歴、眺望の良し悪しといった、その物件だけが持つプラス・マイナスの要因は、公的データには反映されていないのです。
不動産会社は「個別の事情」を評価してくれる
不動産会社が行う「査定」では、データに基づいた評価に加えて、プロの目でその物件の個別の事情を評価に加えてくれます。
査定には、まずデータから簡易的に価格を算出する「机上査定」と、実際に現地を訪問して評価する「訪問査定」があり、特に重要なのが「訪問査定」です。
不動産会社の担当者は、以下のようなポイントを細かくチェックし、査定価格を算出します。
- 建物の内外装の劣化具合、メンテナンス状況
- 日当たり、風通し、眺望
- 設備の状況(キッチン、バス、トイレなど)
- 周辺環境の雰囲気や騒音の有無
これらの個別の強みや弱みを、最新の市場動向と照らし合わせることで、より現実的で「売れる価格」の根拠を持った査定額が提示されるのです。
複数の会社に査定を依頼する「一括査定」がおすすめ
査定を依頼する際に、必ずおさえておきたいポイントが「必ず複数の不動産会社に依頼する」ということです。
なぜなら、1社だけの査定では、その価格が本当に適正なのかを判断できないからです。
売主との契約欲しさに相場より高すぎる査定額を提示する会社もあれば、逆に早く売るために安すぎる額を提示する会社もあるかもしれません。
そこでおすすめなのが、インターネットの「不動産一括査定サイト」の活用です。
物件情報を一度入力するだけで、複数の不動産会社にまとめて査定を依頼できます。
一括査定を利用するメリット
- 手間が省ける:1社ずつ不動産会社を探して連絡する手間がありません。
- 査定額を比較できる:複数の査定額を比較することで、ご自宅の相場をより客観的に判断できます。
- 担当者や会社を比較できる:査定額の根拠や売却戦略を聞き、信頼できる担当者や会社を見つけることができます。
まとめ:家の売却は正確な相場把握から始めよう
今回は、家の売却相場を自分で調べる4つの方法から、価格が決まる仕組み、そしてプロによる査定の重要性までを解説しました。
家の売却を考え始めたとき、何から手をつければ良いか分からず、不安に思うのは当然です。
しかし、今回ご紹介した公的データを活用すれば、不動産会社に相談する前に、ご自身で「おおよその相場観」を掴むことができます。
この自分自身で調べた相場観こそが、売却活動を進める上での羅針盤となり、不動産会社の提示する査定額が適正かどうかを判断する重要な基準になります。
そして、最終的な売却可能価格を知るためには、専門家である不動産会社の訪問査定が不可欠です。
ぜひ一括査定サイトなどを活用して複数の会社の話を聞き、ご自身の大切な家を安心して任せられるパートナーを見つけてください。
この記事が、あなたの不動産売却成功への第一歩となれば幸いです。
AIで不動産査定!
AIがお持ちの不動産の市場相場を診断








