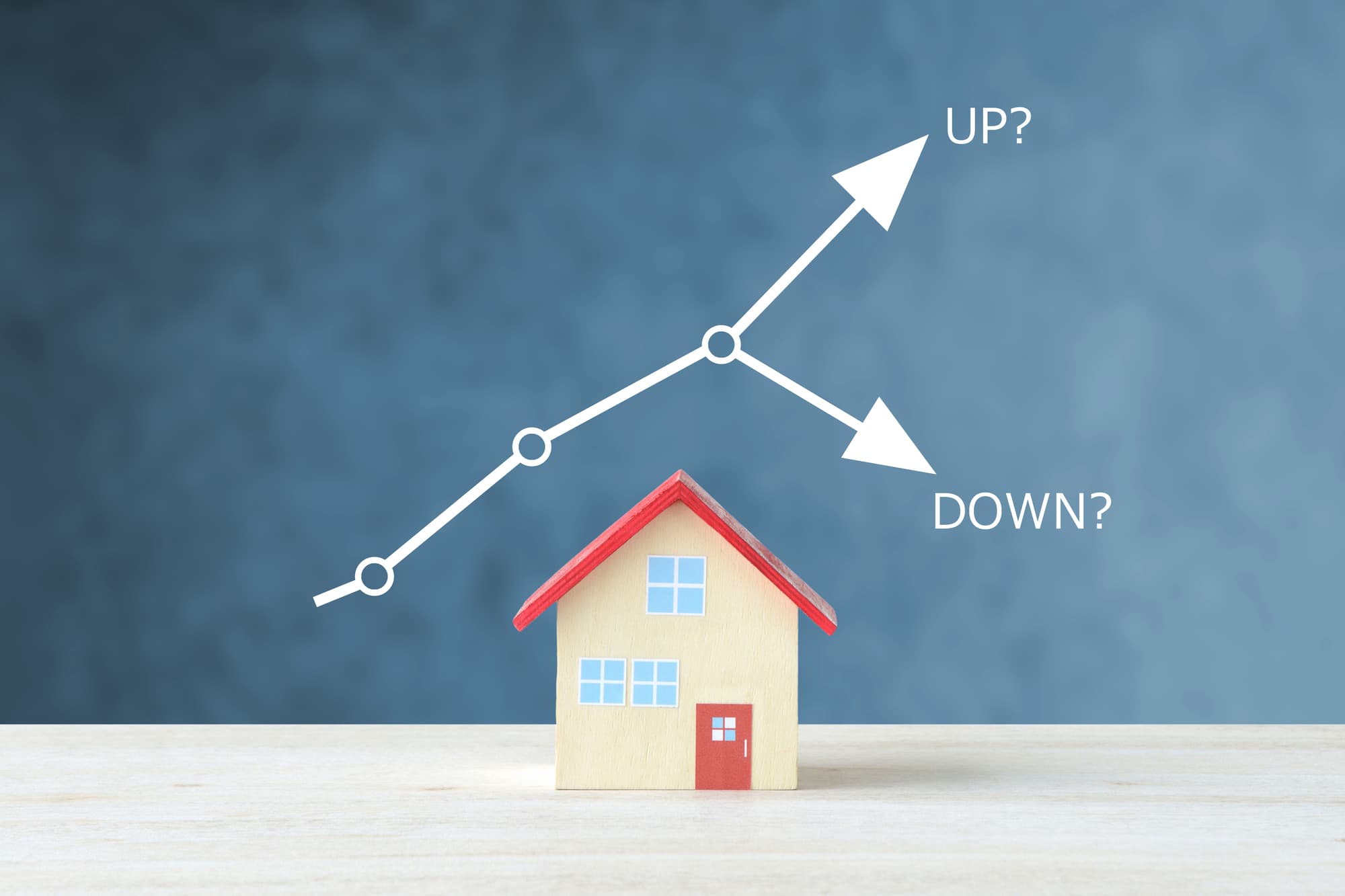
2025年の日本不動産市場は、地域差の拡大や物件種別による価格動向の分岐が顕著になると予想されています。
高齢化や金利上昇などの課題を抱えつつも、都心部のマンションを中心に一部エリアでは引き続き価格上昇が続く一方、郊外や地方では需給バランスの悪化による価格調整が進む見込みです。
以下では、マンション、戸建て、土地の各分野に分けて詳細を解説します。
目次
1. マンション:都心部の高騰と「セカンドベスト」エリアの台頭

- 都心部のマンション
東京23区や大阪市の都心部では、富裕層や国内外の投資家による需要が持続し、価格は年間5-6%の上昇が予測されています。
特に「駅徒歩5分以内」「大規模タワーマンション」など好条件の物件は、資産性と利便性から高値が維持される傾向にあります。
一方で、新築マンションの供給戸数は減少し、2025年は前年比13%増の2.6万戸程度にとどまる見込みです。
要因:建築費の高騰(輸入資材・人件費)、都心部の再開発需要、インバウンド投資の回復。 - 郊外や「セカンドベスト」エリア
都心部の価格高騰を受け、千葉・埼玉・神奈川の都心近郊エリア(例:松戸、柏、相模原)や、東京23区の駅徒歩10~15分圏内の中古物件が注目されます。
これらのエリアは「資産価値の維持」と「手頃な価格」のバランスが取れるため、需要が分散する見込みです。 - リスク要因
金利上昇(変動金利の引き上げ)や管理不全のマンションは価格下落リスクが高く、災害リスクの高い物件も敬遠される傾向にあります。
2. 戸建て:コロナ需要の終焉と二極化

- 需要の減退
コロナ禍で一時的に需要が拡大した戸建て住宅は、2024年以降「失速感」が顕著です。
郊外の一戸建ては価格が横ばい傾向で、中古物件のリセールバリュー(再販価格)の低さが課題となっています。
要因:建築費の高止まり(前年比+2.5%以上)、若年層の都市回帰、資産価値重視の傾向。 - 富裕層向け高額物件の例外
一方、ゆとりある土地を持つ富裕層やデュアルライフ需要(別荘など)では、高級戸建ての需要が堅調です。
ただし、市場全体では「注文住宅」の着工戸数が1959年以来の低水準に落ち込む見込みで、長期的な縮小が予測されます。
3. 土地:都市部の再開発需要 vs. 地方の空き家増加

- 都市部の土地価格
東京・大阪の都心部や再開発エリア(例:渋谷、品川)では、商業施設やマンション用地としての需要が持続し、地価は年間3-5%の上昇が期待されます。
特に半導体企業の進出エリアやインフラ整備が進む地域は、投資家の関心が集まっているようです。 - 地方の空き家問題
全国の空き家率は2023年時点で13.8%と過去最高を記録し、2043年には25%超に達するとの予測もあります。
地方では人口減少が加速し、売却物件の供給過多から地価の下落が続きます。
特に災害リスクの高い地域や管理不全の空き家は、資産価値が限りなくゼロに近づく可能性も指摘されています。
4. 市場全体のトレンドとリスク
- 三極化の加速
「都心部の高騰」「郊外の停滞」「地方の下落」という構図が明確になります。
上位20%の物件が価値を維持する一方、80%は緩やかな下落傾向にあります。 - 2025年問題の影響
団塊世代の後期高齢者化は空き家増加を招きますが、2025年単年での暴落リスクは低いとされます。
ただし、中長期的には不動産市場の縮小圧力となります。 - 金利上昇とインフレ
日銀の利上げ(0.25~1.0%程度)が本格化し、住宅ローンの返済負担が増加。
ただし、インフレが賃料や資産価格を下支えするため、下落トレンドへの転換は限定的と予測されます。
まとめ
2025年は、「場所・物件種別・利便性」の選択が極めて重要です。
都心部のマンションや再開発エリアの土地は引き続き有望ですが、郊外や地方ではリスク管理が不可欠です。
投資家はデータに基づく冷静な分析と、中長期的な視野での戦略が求められます。
AIで不動産査定!
AIがお持ちの不動産の市場相場を診断











